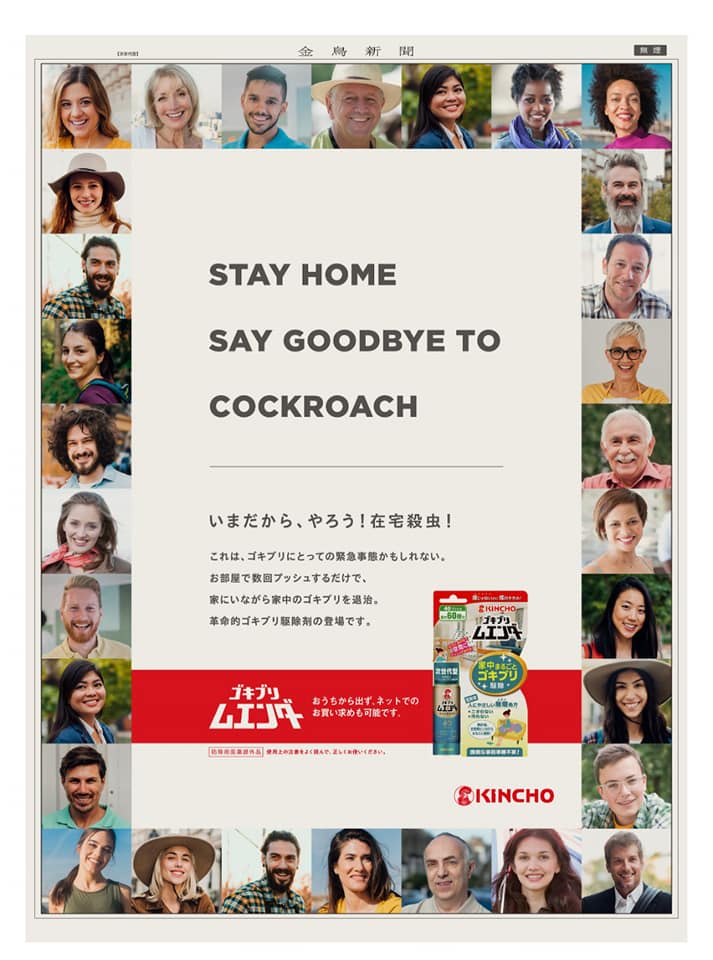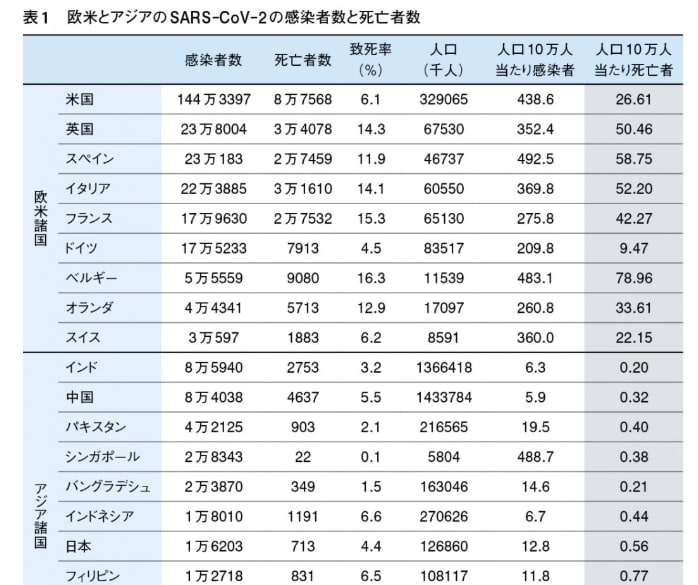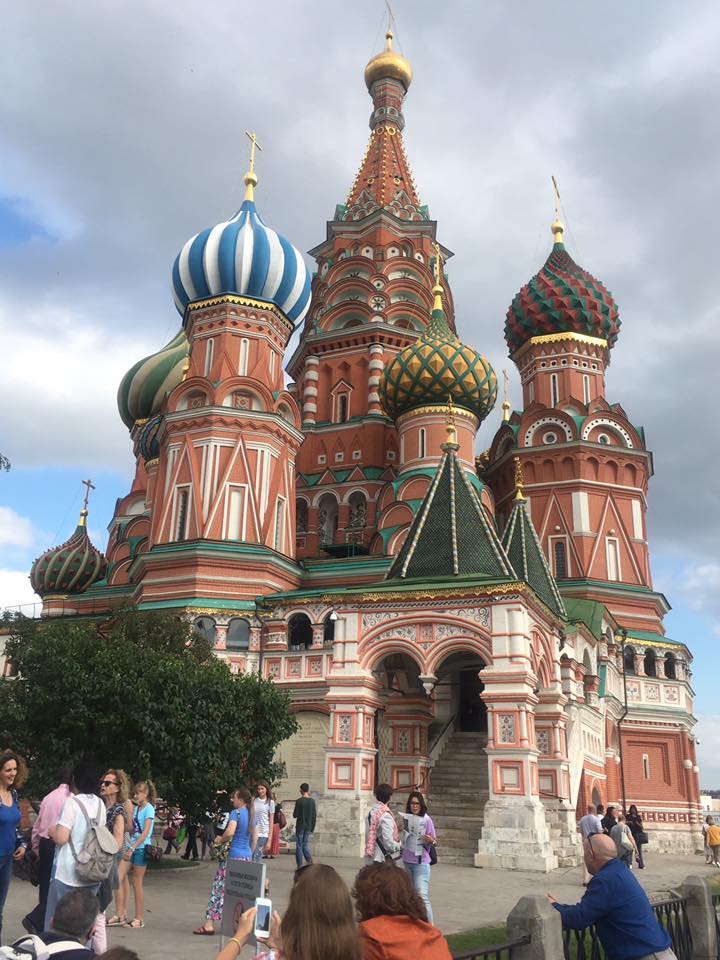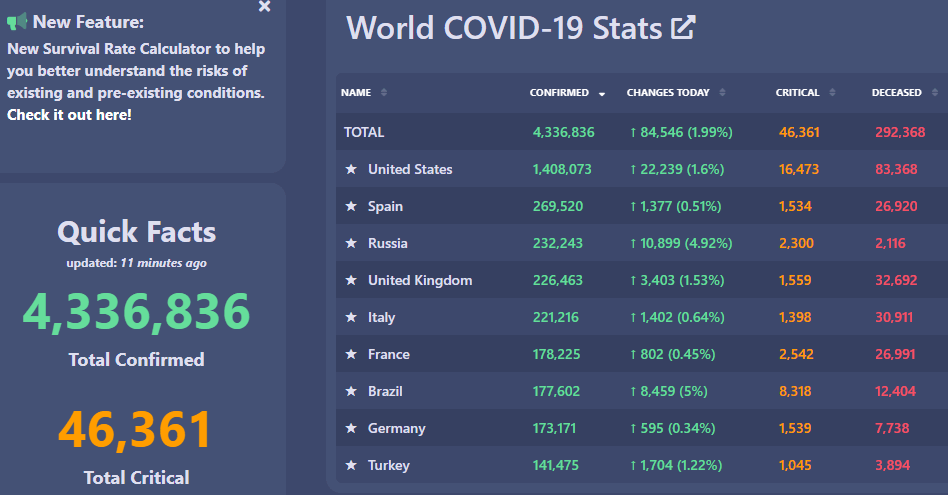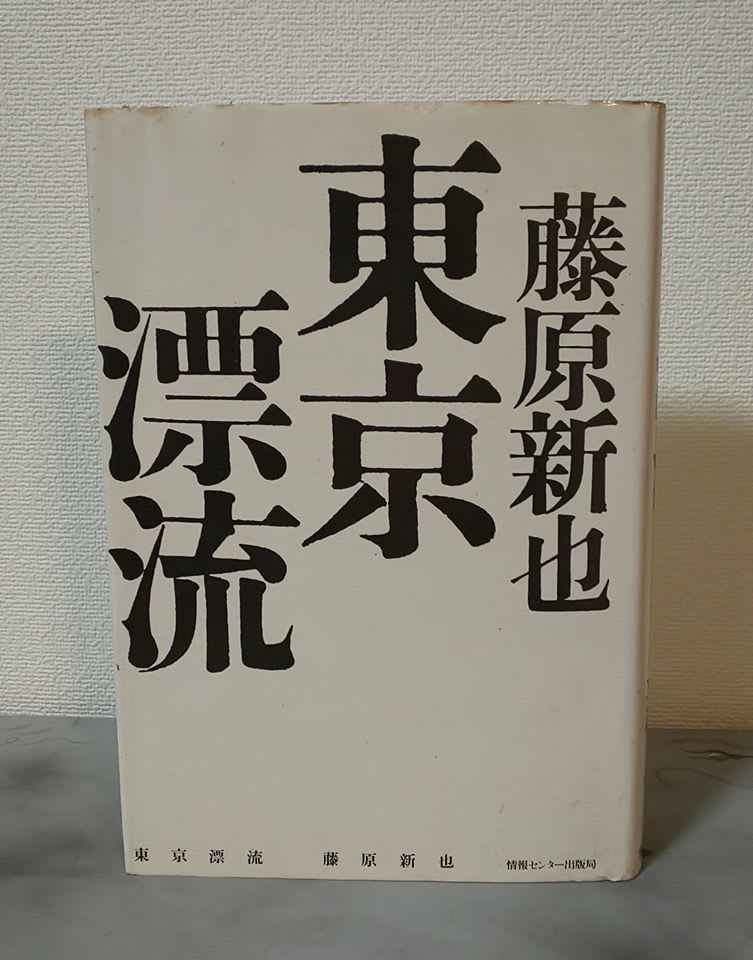昨日観た映画の、原作を読んでみました。
アルツハイマー認知症の父親を抱えた家族の物語があまりにも綺麗に描かれていたので、著者の実体験に基づいて書かれたという原作が気になったのです。
映画と明らかに違うのは、娘が二人ではなく、三人いること。
アメリカの長女の息子が一人ではなく、二人いること。
ストーリーの枝葉末節に細かな違いはありますが、大筋はほぼ一緒です。
深刻な事態を、ユーモアというオブラートで優しくくるんで描いていることも同じ。
といいながらも、やはり認知症の父親の奇異な行動など詳細に書いてあって、これは大変だなあと思わせられるところ、多々。
私が映画で一番納得できなかったのは、認知症の父親を7年(本では10年)にもわたって介護しながら、妻曜子や娘たちが愚痴ったり爆発したり、お互いを責めたりしなかったこと。
そんなことってあるのかと思ってしまったのです。
元中学校長の夫昇平が、同窓会に出かけた筈が会場に辿り着けずに戻って来てしまう。
そこからが始まりだった。
そして病状は年を経るにつれ、どんどん悪化して行く。
言葉を忘れ、徘徊を繰り返し、尿便を漏らし、ベッドから落ちて骨折する。
それでも曜子は老々介護を厭わず、昇平を施設に入れようとはしない。
曜子のこんな独白があります。
”夫がわたしのことを忘れるですって?
ええ、ええ、忘れてますとも。
わたしが誰だかなんて真っ先に忘れてしまいましたよ。
その「忘れる」という言葉には、どんな意味がこめられているのだろう。
夫は妻の名前を忘れた。結婚記念日も、三人の娘を一緒に育てたこともどうやら忘れた。
妻、という言葉も、家族、という言葉も忘れてしまった。
それでも夫は妻が近くにいないと不安そうに探す。(中略)
この人が何かを忘れてしまったからといって、この人以外の何者かに変わってしまった訳ではない”
やはり映画よりも原作の方が、心理描写が細かい分、説得力があります。
昇平は記憶や言葉を失くしたとはいえ、感情的には穏やかであったこと、そして結局、妻や娘たちからこんなにも慕われていたということなのですね。
著者の、父親への深い愛情が伝わって来るようです。
映画にも本にも出て来る、このシーンが私は一番好きです。
まだ病状が初期の頃、昇平がアメリカから来た小学生の孫につぶやくのです。
”「このごろね、いろんなことが遠いんだよ」
「遠いって?」
「いろんなことがね。あんたたちやなんかもさ」
そう言うと祖父は穏やかに小さな孫を見て微笑んだ。”
「
長いお別れ」