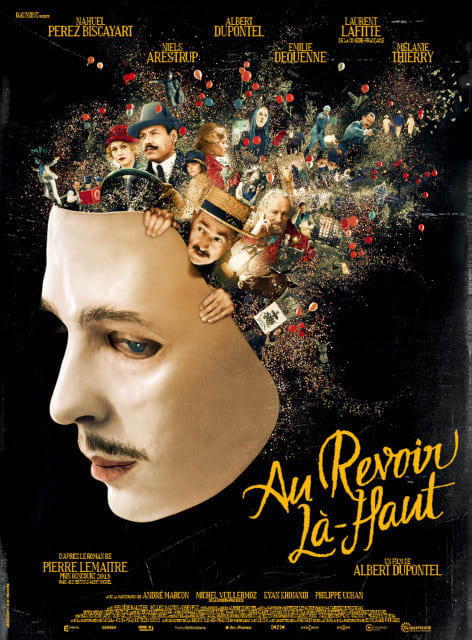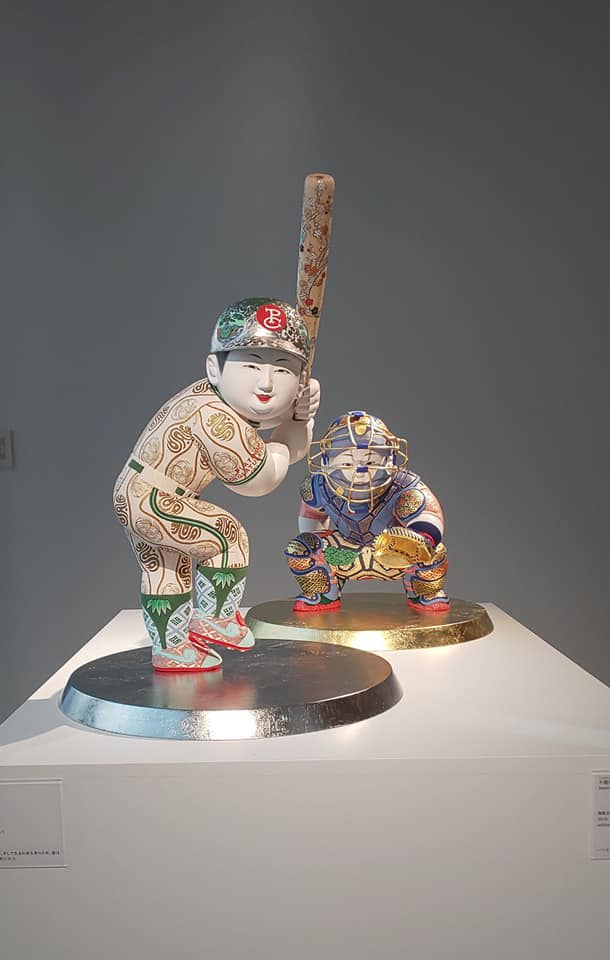グラミー賞を5回受賞した世界的ミュージシャン、エルトン・ジョンの自伝的映画。
監督は「ボヘミアン・ラプソディ」のデクスター・フレッチャー。
1947年、レジー・ドワイトはイギリスの郊外で、厳格で家庭に無関心な父親と
子供に無関心な母親との間に生まれた。
両親に邪険に扱われ、願っても抱きしめて貰えず、孤独を友として成長する。
彼はしかし幼い頃から、一度聴いた曲をすぐにピアノで再現できるという才能を持っており、
同居する祖母にそれを認められ、王立音楽学院に進むことになる。
ミュージシャンを目指す彼はエルトン・ジョンと改名し、曲を作りライブバンドで活躍し、
やがて作詞をするバーニー・トービンと出逢い、二人で美しい歌を作って行く。
監督は「ボヘミアン・ラプソディ」のデクスター・フレッチャー。
1947年、レジー・ドワイトはイギリスの郊外で、厳格で家庭に無関心な父親と
子供に無関心な母親との間に生まれた。
両親に邪険に扱われ、願っても抱きしめて貰えず、孤独を友として成長する。
彼はしかし幼い頃から、一度聴いた曲をすぐにピアノで再現できるという才能を持っており、
同居する祖母にそれを認められ、王立音楽学院に進むことになる。
ミュージシャンを目指す彼はエルトン・ジョンと改名し、曲を作りライブバンドで活躍し、
やがて作詞をするバーニー・トービンと出逢い、二人で美しい歌を作って行く。

あの名曲「ユア・ソング」を作り出すシーンが素晴らしい。
バーニーが書いた詞を読んだ瞬間、エルトンの頭にはメロディが溢れ出て、
譜面に書くにももどかしいほどだったのだそうです。
そして次々に名曲を世に出し、全世界にその名を知られるトップスターとなってゆくのですが、
お決まりのアルコール、ドラッグ中毒、マネージャーの裏切りなどで挫折して行く。

堕ちるところまで堕ちて更生施設に入り、避けていた過去の自分とようやく向き合う。
孤独感やコンプレックスからガチガチに固めていた武装を少しずつ解いて行き、
最後に幼少期の自分を抱きしめるところは感動的です。
最初に画面に現れた時の奇天烈なバードマンの衣装は、彼の最強武装だったのですね。
エルトン・ジョンを演じたタロン・エガートンが実にうまい。
ずんぐりむっくり、若い頃からの薄毛、スキッ歯、お世辞にもカッコイイとはいえない容姿がそっくり。
その歌も素晴らしく(吹き替えなしだそう)、何処を取っても本人にしか見えません。

早い段階でいきなりミュージカル・シーンとなって驚きましたが
その時々の、彼の心象風景をよく表していたと思います。
エンドロールで現在の姿が紹介され、同性のパートナーと結婚して養子を迎え、
幸せに暮らしているということで、救われる思いでした。