
このところのウッディ・アレンの作品はコメディ調のものが続いていて
私には些か物足りなかったのですが、久しぶりにやられました。
主演のケイト・ブランシェット、アカデミー主演女優賞受賞。
ニューヨークで実業家ハル(アレック・ボールドウィン)と結婚し、
何不自由ないセレブ生活を謳歌していたジャスミン(ケイト・ブランシェット)。
夫が詐欺罪で逮捕されたことで無一文になり、すべてを無くして
サンフランシスコの妹ジンジャー(サリー・ホーキンス)の安アパートに転がり込みます。
ところがその飛行機はファーストクラス、荷物は数々のヴィトンのバッグ。
ここで観客は呆気にとられます。
何だ、この勘違い女は!?

NYの豪邸での華やかな生活の回想シーンと、サンフランシスコの安アパートでの生活が
交互に現れ、その対比ぶりが際立ちます。
かつての栄光の思い出にしがみつくだけの日々を送るジャスミンはある時、
金持ちの外交官に出会い、最後のチャンスとばかり彼に賭けようとしますが…
ブランド品に全身を包み、プライドばかり高い姉ジャスミンと
安っぽい服でレジを打ち、ブルーカラーの男とばかり付き合う妹ジンジャーとの対比も面白い。
二人は養子として同じ家に育つのですが
容姿のいい姉ばかり可愛がられ、妹は早くに家出してしまったという経緯があります。
妹ジンジャーはシングルマザーとして二人の息子を育てながら逞しく生きていますが
ちょっと言い寄ってくる男にすぐ気を許して失敗するという、だらしない面も持っている。
ジャスミンは妹の男たちをクズ呼ばわりし、
「あなたは自分を卑下してるから、ダメな男ばかり選ぶのよ」と言い放つ。

つまり姉妹のどちらにも、とても共感することはできない。
そういえばこの作品に出てくる男も女も、およそ好きになれない連中ばかりです。
金持ち男に最後の賭けを挑んだジャスミンは、彼の気を引くために嘘に嘘を重ねて
その結果は当然…
自暴自棄になったジャスミンが思わずつぶやいた言葉。
「一体誰と寝たらウオッカティーニを飲めるの?」
その場にいた妹やその男たち、思わずシーンとなりましたが
この言葉こそジャスミンの本質を表しているような気がします。
偉そうなこと言ったって、つまりそれだけの女なのだと。
酒と薬漬けになったジャスミンは次第に精神の均衡を崩してゆく。
こんなにも救いのない話であるのに
見終わった後、それほど重い気分にならないのは
ウッディ・アレンのシニカルな風刺精神が全編に通低しているからか。
面白がって舌を出しているアレンの顔が見えるようです。
「ブルー・ジャスミン」 http://blue-jasmine.jp/










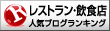
 日立
日立 エレクトロラックス
エレクトロラックス  東芝
東芝  ダイソン
ダイソン




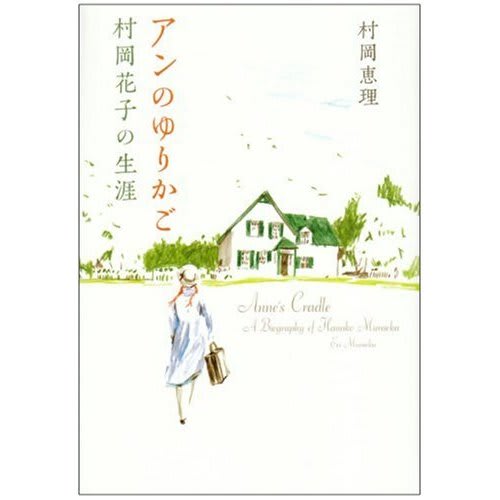














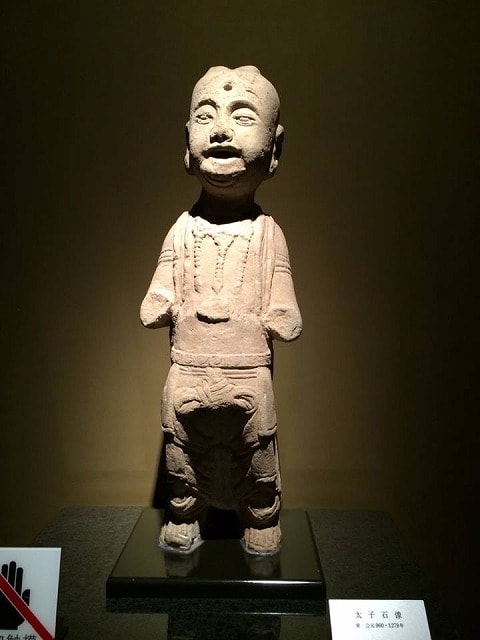








 5cmほどの籠に虫が一匹ずつ入っている
5cmほどの籠に虫が一匹ずつ入っている 5mmほどの虫
5mmほどの虫










