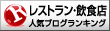村上春樹氏の7年ぶりの長編が、昨日29日発売になりました。
「1Q84」1・2巻、合わせて1000ページほど。
昨夜読み出して夜半に1巻読了、今日の午後に2巻読了。
この本に関しては、先入観を持たずに読んで欲しいということで
発売前の作者へのインタビューでも、内容についてのコメントは一切なかったようです。
なので、私も内容について触れるのはやめようと思います。
最近の彼の著作は、短編集とか翻訳物が多かったので
長編が出るのはやはり嬉しい。
彼の小説は読み出すと、荒唐無稽な世界であっても(或いはそうであるからこそ)ぐいぐいと惹き込まれます。
もっともっとこの世界に浸っていたい、読み終わってしまいたくない、
でもストーリーの顛末は知りたい、早く読みたい!
そのいつもの葛藤も、一日弱で終わってしまいました。
これでまた当分こういう思いはできないと思うと、寂しいなあ…
しかし、この終わり方はあまりに唐突です。
収束できていない伏線も夥しく残ったまま。
この2冊の本が、「上・下」ではなく「1(4月ー6月)」「2(7月ー9月」と
なっていることから、この続き「3・4」が出ることを切望します。
本文の内容に触れられないので
およそ本筋と関係あるとは思えない「気の毒なギリヤーク人」のエピソードを
少々紹介します。
「ギリヤーク人は決して顔を洗わないため、人類学者ですら、彼らの
本当の色が何色なのか、断言しかねるほどだ。
下着も洗わないし、毛皮の衣服や履物は、まるでたった今、
死んだ犬から剥ぎ取ったばかりといった様子だ。
ギリヤーク人そのものも、げっとなるような重苦しい悪臭を放ち、
彼らの住居が近くにあれば、干し魚や、腐った魚のアラなどの、
不快な、ときには堪えられぬほどの匂いによってすぐわかる。
(中略)こうした不健全な衛生環境が彼らの健康状態に悪影響を
及ぼさずにおかぬことは、考える必要がある。
もしかすると背が低いのも、顔がむくんでいるのも、動作に生気がなく、
大儀そうなのも、この衛生環境が原因かもしれない。」
(1巻第20章から)
これは、チェーホフの「サハリン島」からの引用であるらしい。
何故こんなエピソードが恋愛小説に挿入されているのか、不思議に思われた方は
是非本書をお読み下さい。
もっとも、読んだところで、答えなど分からないのですが…
「1Q84」
「1Q84」1・2巻、合わせて1000ページほど。
昨夜読み出して夜半に1巻読了、今日の午後に2巻読了。
この本に関しては、先入観を持たずに読んで欲しいということで
発売前の作者へのインタビューでも、内容についてのコメントは一切なかったようです。
なので、私も内容について触れるのはやめようと思います。
最近の彼の著作は、短編集とか翻訳物が多かったので
長編が出るのはやはり嬉しい。
彼の小説は読み出すと、荒唐無稽な世界であっても(或いはそうであるからこそ)ぐいぐいと惹き込まれます。
もっともっとこの世界に浸っていたい、読み終わってしまいたくない、
でもストーリーの顛末は知りたい、早く読みたい!
そのいつもの葛藤も、一日弱で終わってしまいました。
これでまた当分こういう思いはできないと思うと、寂しいなあ…
しかし、この終わり方はあまりに唐突です。
収束できていない伏線も夥しく残ったまま。
この2冊の本が、「上・下」ではなく「1(4月ー6月)」「2(7月ー9月」と
なっていることから、この続き「3・4」が出ることを切望します。
本文の内容に触れられないので
およそ本筋と関係あるとは思えない「気の毒なギリヤーク人」のエピソードを
少々紹介します。
「ギリヤーク人は決して顔を洗わないため、人類学者ですら、彼らの
本当の色が何色なのか、断言しかねるほどだ。
下着も洗わないし、毛皮の衣服や履物は、まるでたった今、
死んだ犬から剥ぎ取ったばかりといった様子だ。
ギリヤーク人そのものも、げっとなるような重苦しい悪臭を放ち、
彼らの住居が近くにあれば、干し魚や、腐った魚のアラなどの、
不快な、ときには堪えられぬほどの匂いによってすぐわかる。
(中略)こうした不健全な衛生環境が彼らの健康状態に悪影響を
及ぼさずにおかぬことは、考える必要がある。
もしかすると背が低いのも、顔がむくんでいるのも、動作に生気がなく、
大儀そうなのも、この衛生環境が原因かもしれない。」
(1巻第20章から)
これは、チェーホフの「サハリン島」からの引用であるらしい。
何故こんなエピソードが恋愛小説に挿入されているのか、不思議に思われた方は
是非本書をお読み下さい。
もっとも、読んだところで、答えなど分からないのですが…
「1Q84」