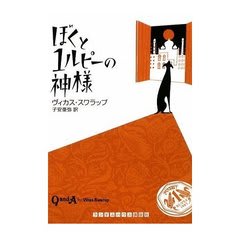一度見たら忘れられない写真、というものがあります。
この写真は、私にとってはその一枚になるだろうなあと思うのです。
ひしと抱き合うホッキョクグマ。
冷たい水に、半身浸かったままで。
「ドイツ、ゲルゼンキルヘンの動物園で初めて顔を合わせたホッキョクグマの
“ビル”と“ララ”は、互いに一目で恋に落ちたようだ。
チェコ共和国の動物園で独身生活を送っていた“ビル”(写真右)は、
結婚相手を探すためにドイツの動物園にやってきた。
元気な赤ちゃんの誕生が待ち望まれている。”
のだそうです。
しかし、素性や動機はどうであれ、このクマの写真には
胸を打たれずにはいられない。
大体、ホッキョクグマって、年中あんな冷たい北の海にいて
なんて可哀想な動物なんだろう?
勿論、彼らにとってはそこが最適の環境だっていうのは分かっているのだけど
それでも、暗く閉ざされた氷の海…
考えるだけでゾッとします。
いくら厚い毛皮に覆われていたって、寒いでしょうね?
私だったら、南のジャングルでノンビリ暮らすナマケモノの方がいいなあ…
そういえば、クマが出てくる童話って、なんだか悲しい話が
多かったような気がする。
宮沢賢治の「なめとこ山の熊」も可哀想な話だった。
あれは北極が舞台じゃないけど。
同じドイツの動物園で人気者になったクヌートの飼育係は、孤独死してしまった。
クヌートは、彼をお母さんのように思っていただろうに。
今でも彼のことを待っているのじゃないだろうか…
等々、一枚の写真を見ながらとりとめのないことを考えてしまいます。
せめて、ビルとララは、幸せになれるといいのだけど。
でも、ララが妊娠したら、ビルはすぐにチェコに戻されちゃうのかしら。
それも可哀想だなあ…
情報元
この写真は、私にとってはその一枚になるだろうなあと思うのです。
ひしと抱き合うホッキョクグマ。
冷たい水に、半身浸かったままで。
「ドイツ、ゲルゼンキルヘンの動物園で初めて顔を合わせたホッキョクグマの
“ビル”と“ララ”は、互いに一目で恋に落ちたようだ。
チェコ共和国の動物園で独身生活を送っていた“ビル”(写真右)は、
結婚相手を探すためにドイツの動物園にやってきた。
元気な赤ちゃんの誕生が待ち望まれている。”
のだそうです。
しかし、素性や動機はどうであれ、このクマの写真には
胸を打たれずにはいられない。
大体、ホッキョクグマって、年中あんな冷たい北の海にいて
なんて可哀想な動物なんだろう?
勿論、彼らにとってはそこが最適の環境だっていうのは分かっているのだけど
それでも、暗く閉ざされた氷の海…
考えるだけでゾッとします。
いくら厚い毛皮に覆われていたって、寒いでしょうね?
私だったら、南のジャングルでノンビリ暮らすナマケモノの方がいいなあ…
そういえば、クマが出てくる童話って、なんだか悲しい話が
多かったような気がする。
宮沢賢治の「なめとこ山の熊」も可哀想な話だった。
あれは北極が舞台じゃないけど。
同じドイツの動物園で人気者になったクヌートの飼育係は、孤独死してしまった。
クヌートは、彼をお母さんのように思っていただろうに。
今でも彼のことを待っているのじゃないだろうか…
等々、一枚の写真を見ながらとりとめのないことを考えてしまいます。
せめて、ビルとララは、幸せになれるといいのだけど。
でも、ララが妊娠したら、ビルはすぐにチェコに戻されちゃうのかしら。
それも可哀想だなあ…
情報元