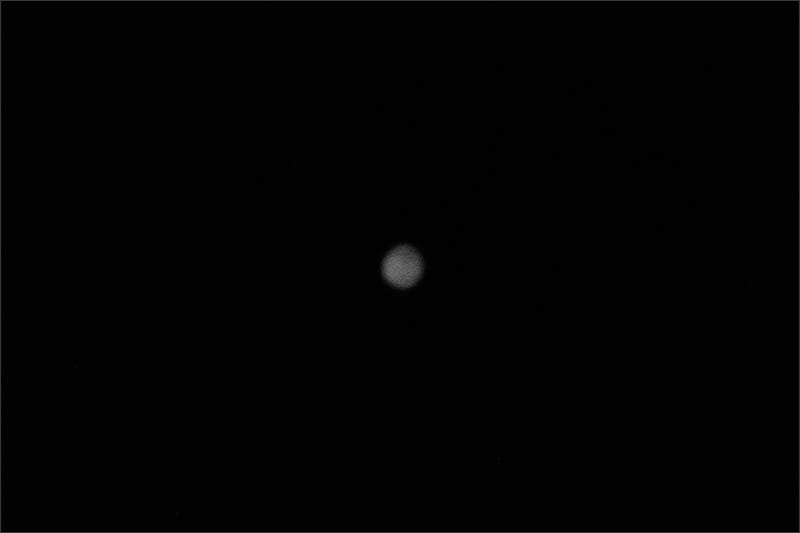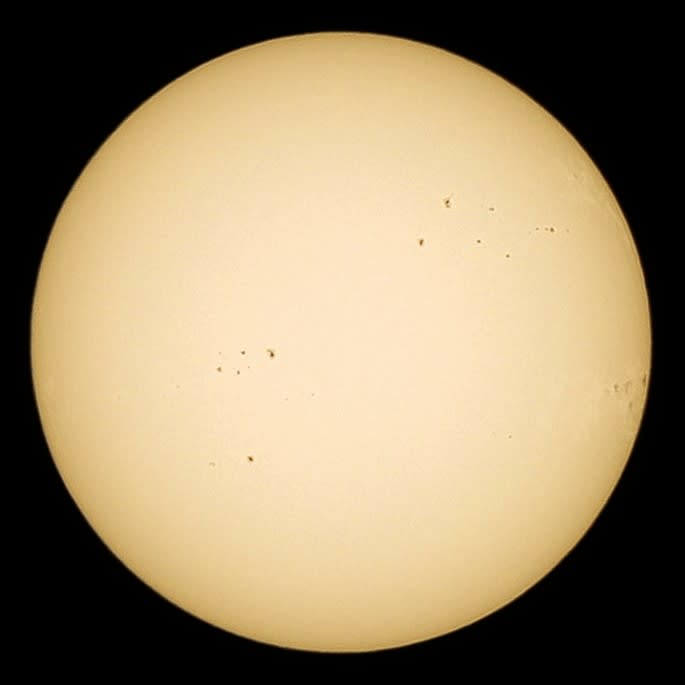【Sh2-298】
赤経:07h18m38s 赤緯:-13゚11' 55"
星座:おおいぬ座
視直径:22'
他カタログNo.:NGC2359
ニックネーム:トールの兜(かぶと)星雲(Thor's Helmet nebula),アヒル星雲(Duck nebula)
南中日時(@東京):11月22日03時,1月6日00時,2月20日21時 ※あくまで目安です。

撮影日時:2019/04/06 19:36
撮影地:静岡県東伊豆町
撮影機材:キヤノンEOS60Da+タカハシε-180EDC,アイダスNB1フィルター使用,
タカハシEM-200Temma2M赤道儀,ペンシルボーグ+QHY5LⅡM+PHDにより恒星ガイド
撮影条件:ISO1600,露出7分×8コマ
画像処理:Digital Photo Professional4にて現像,ステライメージVer.8,Photoshop2024にて処理
トリミングあり
メモ:おおいぬ座の北東部、いっかくじゅう座との境界近くにある散光星雲です。西側の明るい部分
が北欧神話に出てくる雷神トールが頭にかぶっている兜のように見えることから、それが愛称
として付けられています。また、高輝度部の円形領域とその南にある突起部を鳥の頭部と嘴に
見立て、アヒル星雲と呼ばれることもあります。ウォルフ・ライエ星という特異な星が外層の
ガスを放出することで形成された星雲と考えられており、複数の元素が異なる輝線で発光して
いるため、写真では暖色系(主に電離水素の発するHα光)と寒色系(主に電離酸素の発するOⅢ
光)の対照的な色が混在した姿として捉えられます。それらの輝線波長だけを選択的に透過する
デュアルバンドパスフィルターを使って撮ると、上の写真のように東側の淡い部分の広がりも
描出することができます。淡いので小口径望遠鏡での観望対象にはなりませんが、口径40~
50cmクラスの大きな望遠鏡と、電離酸素の発する輝線に合わせたOⅢフィルターを用いれば、
眼視確認できるようです。
星図:

AstroArts社ステラナビゲータにて作成