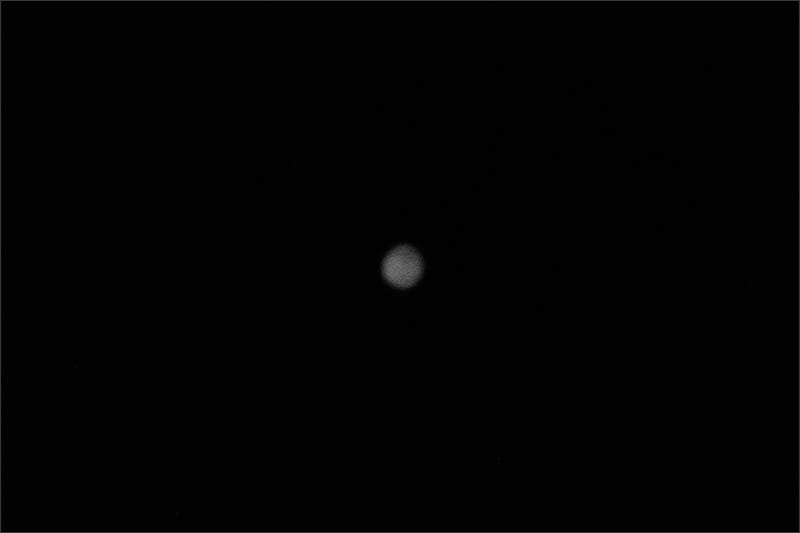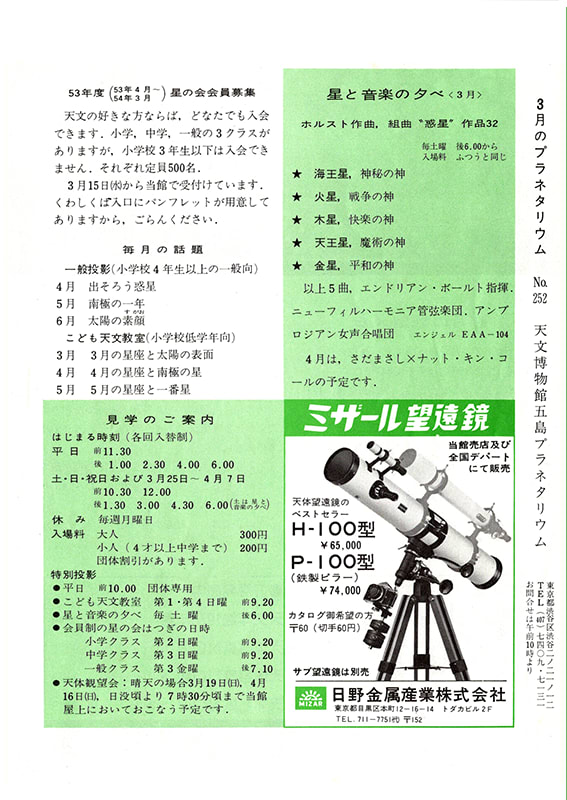昔の銀塩写真のデジタル化画像シリーズの続き(第11弾)です。
1982年3月は「惑星直列」が話題になり、報道等でよく見聞きする流行語みたいになってました。
これは太陽系の惑星が狭い扇形の角度範囲(90゚?)に入る現象のこととされ、全惑星が一直線に並ぶ訳ではありません。
特に重要な天文現象でもないのですが、惑星同士の引力の相互作用により地球上で天変地異が起こるといった噂が
巷で広まり、恐怖心を煽られる人もいたようです。関連性は不明確ですが、同月末にメキシコのエルチチョン山が
大噴火し、多数の死傷者が出ました。日本では大きな事件/事故が目立ち、2月にホテルニュージャパンの大火災と
日航機の羽田沖墜落事故が立て続けに起こったりした時期にあたり、不吉な事の前兆だと関連付ける人もいましたが、
年間を通じて大きな自然災害などはありませんでした。
個人的には某大学への進学が決まって入学準備もほぼ完了した頃で、久々に天体撮影に勤しむ機会が作れました。
話題の「惑星直列」は、天文ファンにとっては外惑星が同一の夜空にまとめて見える観測チャンスということで、
惑星のクローズアップ写真を撮ってみようと思い立ったのでした。ちなみに、当夜遅くの夜空はこんな状況。

AstroArts社ステラナビゲータによるシミュレーション
この時期、南東天に昇ってきたおとめ座に火星と土星、隣のてんびん座に木星が輝いていたんです。
それらの3惑星を反射望遠鏡+アイピース拡大撮影用カメラアダプター+一眼レフカメラを用いて上から順番に
撮影していきました。
まずは火星から。

【火星】
キヤノンEF+タカハシ13cmパラボラニュートン反射+Or7mmアイピース,コダックTri-X(ASA/ISO400),
F66,露出1/30秒,タカハシ90S赤道儀使用,トリミングあり,都内某所にて
約2週間後に衝(太陽と正反対の方向に来る状態)となる時期で観測好期を迎えてましたが、この年は小接近だったため
あまり大きく見えず、とりあえず面積体には写りましたけど模様などは全く確認できないイメージでガッカリでした。
次は土星。

【土星】
キヤノンEF+タカハシ13cmパラボラニュートン反射+K9mmアイピース,コダックTri-X(ASA/ISO400),
F43,露出1/8秒,タカハシ90S赤道儀使用,トリミングあり,都内某所にて
火星よりも暗いので拡大率を少し抑えてF値を小さくし、シャッタースピードは遅めに設定して撮りました。
環が何とか確認できるイメージが得られましたけど、眼視で覗いて見た姿よりも劣る感じで、これにもガッカリ・・・
最後は木星です。

【木星】
キヤノンEF+タカハシ13cmパラボラニュートン反射+Or7mmアイピース,コダックTri-X(ASA/ISO400),
F66,露出1/15秒,タカハシ90S赤道儀使用,トリミングあり,都内某所にて
木星は明るいので拡大率を元に戻して撮影。縞模様が分かるので、まあ満足できるレベルかなっていう印象でした。
惑星の拡大撮影は月の拡大撮影とほとんど変わらないって舐めてた自分が間違いだったことを痛感しました。
まずは拡大率をもっと上げないとダメだなぁーって思ったのでした。