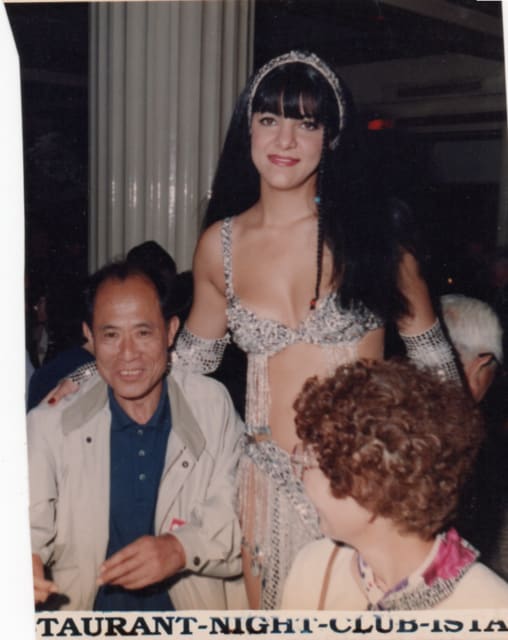ガンディー(1859~1948)は非暴力の抵抗でインドの独立を勝ち取った人としてインド建国の父として世界的にも著名な人物であるかとは常識ですね。その彼の火葬場がデリー郊外に残されていて(写真)インド人の礼拝の場となっています。ヒンズー教は墓を作りません。したがって彼の墓もありません。
ついでの話ですがヒンズー教の親戚の仏教徒にも墓はありません。日本では「仏教=墓」というイメージがありますが、日本だけが特殊で日本以外の仏教徒は墓を作りません。
「お墓があるのは、仏教国では日本だけである。日本人は仏教と言えば、お墓を連想するほど、仏教にとっては不可欠なもの、仏教の一部だと思い込んで、お墓のない仏教など夢想だにしない。しかし、現在仏教が信奉されているアジアの各地を訪れれば明らかのようにお墓はどこにもない」(今枝由郎著『ブータンから見た日本仏教』p115)
もひとつ余談話。最近遺骨の取り違えが話題になっていますが、本林靖久氏はその著「ブータンと幸福論」(p135)で「(日本人は)葬送儀礼においても骨に対する執着が強すぎ、死者の儀礼の行きつくところが、遺骨の処理や保存に囚われすぎではないかと思う」と述べています。
ガンディーの話に戻ります。彼はイギリス留学を終えてアフリカに行ったとき差別を受け、始めてインド人意識に覚醒して、そこからインド独立を考え始めます。
このガンディーのインド人意識の覚醒の時、南アフリカ原住民への差別についてガンディーはどう考えていたのかが、わたくしの長年の疑問でした。1999年に大阪外国語大学助教授秋田茂氏の論文「植民地エリートの帝国意識とその克服」(「大英帝国と帝国意識」の内の論文)に関連して秋田氏に質問をしました。以下氏の回答文の一部
「***ガンディーの関心は、もっぱら在住インド系住民の権利擁護に向けられており、現地人については、意識的に無関心を装っていた。あるいは、関心を振り向けるだけの余裕はとてもなかった、というのが実情ではないでしょうか。私も今回の論文では、ご指摘の点は少し意識しておりましたが、十分にフォローできませんでした」