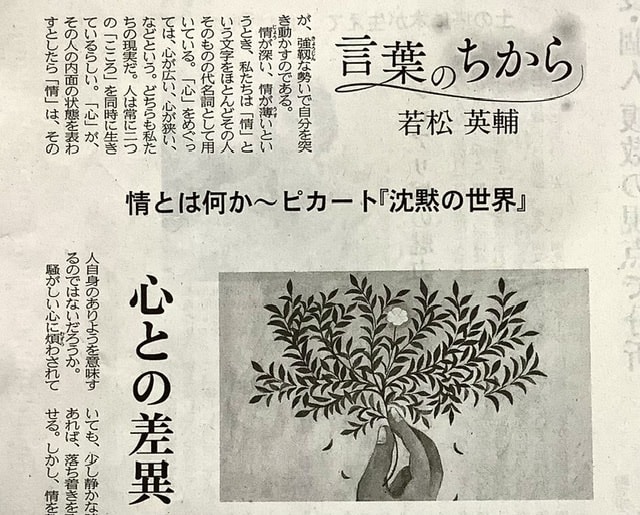
5月27日の日経朝刊に、若松英輔の「言葉のちから」というコラムが載っていて、これについてずっと考えています。記事の一部を書き写したものを、まずはご紹介します。
情が深い、情が薄いというとき、私たちは「情」という文字をほとんどその人そのものの代名詞として用いている。 「心」をめぐっては、心が広い、心が狭いなどという。 どちらも私たちの現実だ。人は常に二つの「こころ」を同時に生きているらしい。「心」が、その人の内面の状態を表わすとしたら「情」は、その人自身のありようを意味するのではないだろうか。(中略)情の世界を描こうとするとき、言葉に技巧を凝らしてもうまくいかない。情が顕現するのは文章の内容であるよりは文体においてであり、発言においてであるよりも、その人が醸し出す雰囲気や間においてなのである。
記事を反芻しているうちに、最近読んだばかりの、こんな話を思い出しました。
昭和16年、当時日本の領土だった北朝鮮から日本に向かっていた定期貨物船「気比丸」が、ソ連の敷設した機雷に触れて沈没し、京大哲学科学生、弘津正二が船とともに沈んだ事件です。当時の新聞によると、早く救命ボートに乗るよう言われながら「どうぞお先に」と言って先を争わず、ついに助からなかったのだと言います。また弘津は京大図書館からカント全集中の2冊を借りて実家に戻っており、それを取りに行ってボートに間に合わなかった、という推測も生まれました。
その行動は多くの人に感銘を与えたのですが、その事件後33年経った昭和48年の読売新聞に次のような記事が載せられました。乗客が救命ボートに殺到するなか、同船に乗っていた警官がピストルをかまえ「乗るのは内地人だけだ」と朝鮮人を制したのを見た弘津がこの態度に義憤を禁じ得ず「私は朝鮮の人たちと行動を共にする」と言って船内に残ったというのです。
その年の『文藝春秋』にこの読売新聞の真偽についてのルポが掲載され、遭難現場に急行した砲艦の乗組員が、生存者から聞いた証言が掲載されています。「学生が一人、本を見ながら甲板を離れず、船と共に沈んだ」そして、その話は救助に向かった艦内で持ちきりだったと。
話がだいぶ長くなりましたが、これは長らく絶版されていて、昨年41年ぶりに復刻された名著『カント講義』(高峯一愚著 論創社)に紹介されていたものです。
「どうぞお先に」と言ってボートを譲った姿、大学の蔵書を取りに戻った姿、自分は朝鮮人と行動を共にすると言い放った姿、どれも心を打つ話に違いはありませんが、それは若松英輔の言う「心」についての記述ではないかと思います。どれも技巧を凝らしてうまく書くことのできる話です。
人はその技巧を競って語ろうとしますが、いつまでも人のこころに残るのは、生存者の「学生が一人、本を見ながら甲板を離れず、船と共に沈んだ」という証言です。そこからは「情(こころ)」が静かに伝わってきます。
前掲書『カント講義』は全体に、カントの言説に沿ってまとめているのですが、道徳原理について語る「実践理性批判」の説明では、唐突に「気比丸事件」が取り上げられています。
「言葉に技巧を凝らしてもうまくいかない」という若松英輔の指摘どおり、著者は語りの姿勢を変えています。そうすることで、静かに共有する「間」や「雰囲気」をこそ描こうとしたのだと思います。




















