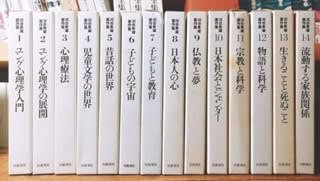多大な経済的損失をもたらしたコロナ禍も、同時にじっとしている時間を私たちにもたらしました。この間、多くの本を読むことができましたが、そのなかで、最も長い本がリチャード・パワーズ著『オーバーストーリー』(新潮社 790頁)でした。
前に当ブログで触れたことがありますが、今この時期に思うこともあって、少し詳しくご紹介したいと思います。
樹木とそれを守ろうとする人たちの物語なので、その手のイデオロギーにまみれた本のような印象を持たれてしまうかもしれませんが、内容は全く違います。
森林の空間や地中には、おびただしい数の菌類や小動物がいて、それぞれが情報網となり、化学物質の伝達を行いながら、森林全体を「巨大な知性のネットワーク」として活動させています。科学者、過激派、技術者、元空軍兵士などの登場人物たちは、そのネットワークの一部になろうとするかのように、物語は展開していきます。
彼らは木を伐ろうとする人たちとの戦いにおいて圧倒的に無力なのですが、やがて樹木に導かれるように、したたかになることを学んでゆきます。
本書のなかには、王維の詩『酬張少府』が何度も引用されていて、それが全体の通奏低音のように響いています。
晩年唯好靜 萬事不關心 (晩年唯だ静を好みて 万事心に関せず)
自顧無長策 空知返舊林 (自ら顧るに長策無く 空しく旧林に返るを知りぬ)
松風吹解帶 山月照彈琴 (松風吹けば帯を解きて 山月照らせば琴を弾ずる)
君問窮通理 漁歌入浦深 (君が窮通の理を問わば 漁歌は浦の深きに入ると)
まるで世捨て人の詩のようですが、結句の「漁歌」は屈原の『楚辞』のなかの歌であって、その歌に当たってみると印象が全く変わります。私も調べてみて初めて気が付きました。『楚辞』漁父にはこう記されています。
滄浪の水清らかなら冠の紐を濯うべし 水濁らば足を濯うべし
(滄浪の水の流れがきれいなときは冠のひもを洗おう、
濁っているならば足を洗おう)
状況に応じて、したたかに生きていこうと屈原は歌います。どんなに巨大な相手が、理不尽な行為に及んでも、したたかに生きていこう、と。
小説で引用される詩の結句は、屈原の「漁歌」を受けて説得力を持ちます。したたかに生きることを、著者は「うまくいく可能性を探る」とも表現しています。小説の主人公のひとりで、樹木のコミュニケーションを説く科学者は、講演のなかで次のように語っています。
少しでもうまくいく可能性がある戦術はすべて、いずれかの植物が過去4億年の間に試しています。私たちは今ようやく〝うまくいく〟というのがどれほど多様な意味を持つのか気付き始めたばかりです。生命というのは、未来へ語り掛ける方法なのです。それは記憶と呼ばれます。あるいは遺伝子と呼ばれます。未来という問題を解くには、過去を保存しなければなりません。
本書がエコロジー的な観点からの啓蒙書という枠組みにとどまらないのは、巨大な敵に対して敵と同じロジックに拠って戦うのではなく、状況に応じてしたたかに生きることを描いているからだと思います。
本書を読み終えたのは、ちょうど香港で学生たちが逮捕され弾圧を受けている時期だったので、本を閉じてしばらく彼らのことを考えていました。彼らが「うまくいく」ことについてです。そして今、ウクライナで起きている理不尽な事態を目の当たりにして、本書を改めて思い出しました。
私たちは、あまりにも早急に、分かりやすくものごとを理解しようとしてきたのではないか。そして、過去を振り返ることを、あまりにも、おろそかにしてきたのではないか。同時にそうも考えました。