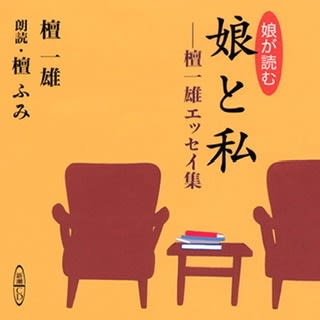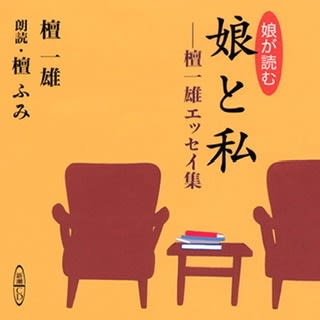
ポルトガルのサンタ・クルスで2年間を暮らして帰国した檀一雄は、1974年福岡市の能古島に転居しました。そこで「人生の刈り入れに向かうつもりだ」と書き残しての移住です。ちょうど、わたしの今の年齢と同じ62歳だったと思うと、感慨深いことひとしおです。
檀一雄には『娘たちへの手紙』という小文があって、わたしは若い頃から何度もこれを読み返してきました。
檀ふみさん朗読のCD『娘と私 檀一雄エッセイ集』(新潮社)の「成人の日によせて」の項に収録されていますし、新潮社の『檀一雄全集第8巻』に収められています。ちなみに当ブログの引用元『日本の名随筆49 父』(作品社)は残念ながら絶版です。
エッセイの出だしはこうです。
これから、九州の島に帰るつもりなので、その前に、私は、お前達に、今までまだ書いたことのない手紙を、書き残していこうと、思う。
そのおろかな父から、人生の門出に向う、娘達への手紙である。
たとえてみれば、私のお前達に対する遺書である、と思ってみても、さしつかえはない。(『日本の名随筆 父』165頁)
「私のお前達に対する遺書である」とはっきり書いているのは、今回読み返してみて改めて気付きました。娘達への溢れるばかりの愛情が読み取れる文章ですので、少し長くなりますが引用させていただきます。成人の日にふさわしい文章だとも思います。
たとえば、お前達は、庭先に群れをなして、這っているおびただしい蟻の列を見る。指でひとひねりすれば、それでコトキレ、一瞬にして、蟻は死ぬ。あたりは、空漠であり、その空漠の中に、破壊されたものが、なんであったか‥‥‥。解答はまったくない。
我々、ひしめいている人間のひとつひとつの命のありようも、全くこれと同じである。
「お幸せに……。」も「おかわいそうに……。」もない。あらゆる生命は、神から放たれたか、生産する自然力とでもいったような根源の力から生み出されたのか、知らないが、その無限の造物の力によって、まるで、みじめな、それぞれの道化を演じさせられるあんばいに、この地上にほうり出されて、ある。
その有限の生命どもが、泣いたり、笑ったり、怒ったり、裏切ったりしているわけだが、どのような修飾の言葉で装ってみても、人は生まれ、這い這いし、立ち上がり、ツヤヤカになり、やがて、男は女を追い、女は男を迎えて、やれカケガエない……だの、やれ絶対……だの、と口走りながら、有頂天になるヒマもなく、いつのまにか、もう老いの影に脅え、ひとりひとり、よろけながら、死んでゆく……。
もっとも普通の「お幸せにね……。」が円満に実現されるとして、けっしてこれ以上のものではないはずだ。
悲しいけれども、人間は、たったこれだけのものである……、ということを、まず、知るべきだろう。いや、必ず、知ることになる。
だから、私はお前達に、早く人生に絶望せよ、といっているわけでは、けっしてない。
いや、その反対だ。
まことにみじめではあるが、私達一人一人に、イノチという、自分だけで育成可能のなんの汚れもない素材が与えられている。
お前達一人一人は、そのよごれのない一つずつの素材を与えられた、芸術家であり、教育者であり、いってみれば、自分自身の造物主であり、いや、ちっぽけな、哀れな、神ですらあるだろう。なぜなら、おまえたちのイノチのありようは、おまえたちが選ぶがままであり、おまえたちのイノチの育成も、おまえたちの育成するがままだからだ。(166頁)
ちっぽけな造物主としての人間には、しかし「青春」というものが「もっとも動物的な形で殺到してくる」のだし、「絶対の愛」などを求めても、みじめで有限な生き物であることを、ひたすらに思い知らされるだけです。壇はそう語ったあと、それでもいいではないか、一敗地にまみれることがあっても、それは大きな自己育成の転機だろうと、次のように語ります。
そのはかない、過ぎやすい、一瞬の逢縁(出合い)を、静かな、充実した、かけがえない時間の喜びに変えることは出来る。
それは、お互いの自己育成の果てに、ようやく知る一瞬の、かけがえなさの自覚からである。
寛容と敬愛は、おのずから、やすやすとした信頼の交互作用を生んで、人間なにものであったか……、のほこらしい安堵に近づくかもわからない。
しかし、これは、万に一つの愛のカタチであって、おそらく、泥にまみれ、地にまみれた、男女らの、長い、自己育成の果ての夢に近いかも知れぬ。
しかし、ためらうな。恐れるな。悲しみをも享楽出来るほどのイノチを鍛冶して、自分の人生に立ち向かっていくがよい。(168頁)
本文中に自らを「頑父」と呼ぶように、厳しい言葉のように見えますが、これほど慈愛に満ちた言葉を知りません。わたしがもっとも好きなのは最後に語られる次のフレーズです。娘達を愛しむ気持ちが、隠されることなく表現されています。
お前達の前途が、どうぞ、多難でありますように……。
多難であればあるほど、実りは大きい。(169頁)
人生の門出に立つ娘達をいつまでも見送る、父親の後ろ姿がありありと目に浮かびます。