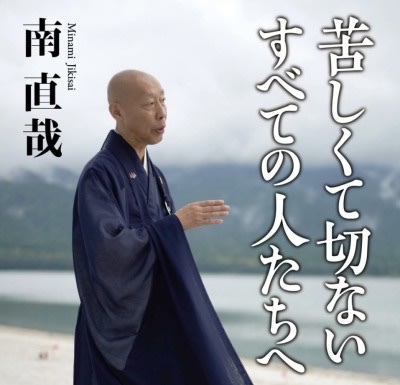福岡城の天守閣を建築しようとする動きが、このところ活発で、その一環として天守閣の形を鉄パイプで櫓状に組み上げ、桜まつりの期間、ライトアップするという企画がありました。
ライトアップは先月までなので、パイプの櫓がどうなっているか見に行ったところ、まだ形を残していました。

天守台に続くだらだら坂を降りると、多聞櫓という史跡の石垣の下に、菖蒲の花が群生しています。

夜の暗渠みづおと涼しむらさきのあやめの記憶ある水の行く
(高野公彦)
夜の暗渠のなかを、あやめが咲き誇ったであろう水源の記憶を携えて水が流れてゆく、その水音は涼しいと歌人は詠います。
あやめの記憶を連れた水は紫色に染まってはおらず、その流れる水音は暗渠のなかなので、地上から聴こえるはずもありません。けれども、この歌を読むと、あやめの紫のエッセンスと群生の記憶を凝縮した水が、さらさらと流れる音が聴こえるようです。「みづおと」となって今に触れ合うからこそ、記憶がよみがえるのです。
記憶というものは、視覚よりも聴覚や嗅覚、味覚などで爆発的に蘇るものだと思います。
ちょうどこの時期であれば、雨傘のカビ臭い匂いがすると、子供時代、土曜日の半ドンの帰り道を、仲の良い友達4人で傘をさして帰ったときのことを、ありありと思い出します。通り過ぎた家からは「松竹新喜劇」のテーマソングが流れていました。
ちなみに、菖蒲の群生する水辺や、南側住宅地を水源とした水流が、暗渠となって道路の下を流れ、たった1キロのあいだ菰川という名前になって姿を現した後、博多湾に注いでいると聞いたことがあります。そういうわけで、暗渠を流れるあやめの記憶という、突飛な取り合わせも、当地ではリアルな姿となって思い浮かべることができるのです。あやめ記憶をたたえた水音さえ聴こえるような気がします。
福岡城の天守閣建築の話は、特に経済界で盛り上がっているらしく、見栄えのする史跡の乏しい福岡市にとっては、経済波及効果の期待できるプロジェクトのようです。幕府謀反の嫌疑を恐れて直ちに取り壊したとか、そもそも最初から建っていなかったなどと、本当のところが分からないので、これまで建築に踏み切ることができないでいました。
私としては、視覚にのみ訴える偽物の記憶をつくりあげることよりも、桜まつりの期間だけのライトアップの幻に終わらせてはと思うのですが。