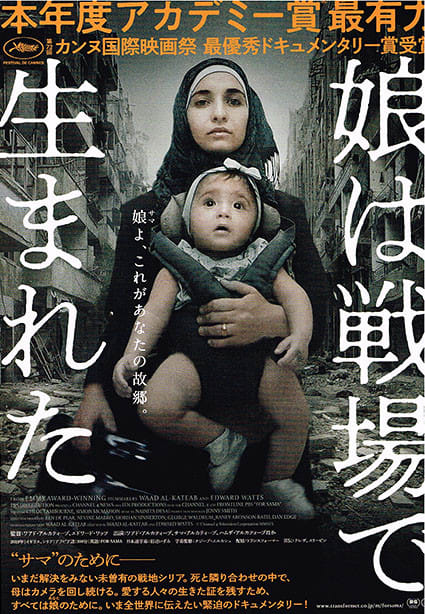人の心を動かす、実にいい映画!
「黒い司法」78点★★★★



*********************************
1986年。米アラバマ州で木材所を営む
ウォルター・マクミリアン(ジェイミー・フォクス)は
仕事から帰る途中、いきなり逮捕される。
地元で女子大生が殺害された事件の
犯人にされたのだ。
まったく身に覚えがないウォルターだが
あっという間に死刑判決が決まってしまう。
それは
「白人女性を黒人が殺した」としてケリをつけたい保安官、
さらにはそこに同調する世間の恐ろしい空気が、招いた結果でもあった。
おなじころ
1988年、ハーバード・ロースクールを出た
弁護士ブライアン(マイケル・B・ジョーダン)は
リッチな将来には目もくれず、
特に人種差別激しい南部で
えん罪などに苦しむ人々のために力になりたいと、アラバマにやってくる。

そしてブライアンは、死刑囚監房にいるウォルターに出会い
彼の無実を晴らそうと考えるのだが――?!
*********************************
いや~これはいい映画でした。
1988年、死刑判決を受けた黒人男性の無実を晴らそうと
不可能とされた闘いに挑んだ
実在弁護士の物語。
てか、1988年って、つい最近ですよ?
こんな素晴らしい人物がいたことを、
知らなかったことに、驚いた。
人種差別根強い、南部アラバマで
無実の罪で死刑になろうとしているウォルター。
彼の無実を証明しようと奔走する
若き弁護士ブライアン。


法廷モノはハラハラで大好きだけど
これほどに「いや、これはムリじゃね? 」と思わされる案件も珍しい。
」と思わされる案件も珍しい。
たいした証拠もなく捕まったウォルターだけに
無実を証言できる要素はあって
最初は、そんなに大変ではないように感じるんです。
が、そこに想像を絶する壁が立ちはだかる。
ウソをついて、ウォルターを犯人にした保安官たち、
そして「黒人を犯人にしてしまえ」と加担した権力側は
なんとしてでも、そのウソを突き通す必要があり
もう手段を選ばないんですわ。
証拠は消され、
真実を語ろうとした者は職を奪われ、
あろうことか逮捕されたりもする。
ブライアンをサポートするアシスタント(ブリー・ラーソン)をはじめ
協力者は脅迫される。
真実の光が見えた! かと思えば、
かと思えば、
忖度があり、絶望に突き落とされるんです。
さすがにこれはダメか―― と観客も虚脱するはず。
と観客も虚脱するはず。
でも、ブライアンは諦めないんです。
えらい。えらすぎる。
「正義を貫くには、理想だけではだめだ、強い信念と希望が必要なのだ」と
邪悪なウソを突き続ける巨大権力に立ち向かうその姿、
まさに、いまの日本に突きつけたい!
凜とまっすぐな正義を体現した
弁護士ブライアン役のマイケル・B・ジョーダンは
2009年に黒人青年が警官に殺された事件を基にした
「フルートベール駅で」(13年)(超・良作!)の主演の彼です。
うお、ますますイケメンになった、と思いつつ
奇しくもこの作品と、つながってるテーマであるところにも
感銘を受けました。
現代も、闘いは続いているのだ。
★2/28(金)から全国で公開。























 、意外に商才があるんですわ(笑)。
、意外に商才があるんですわ(笑)。 のオークションのスリルが重なっていくんです。
のオークションのスリルが重なっていくんです。