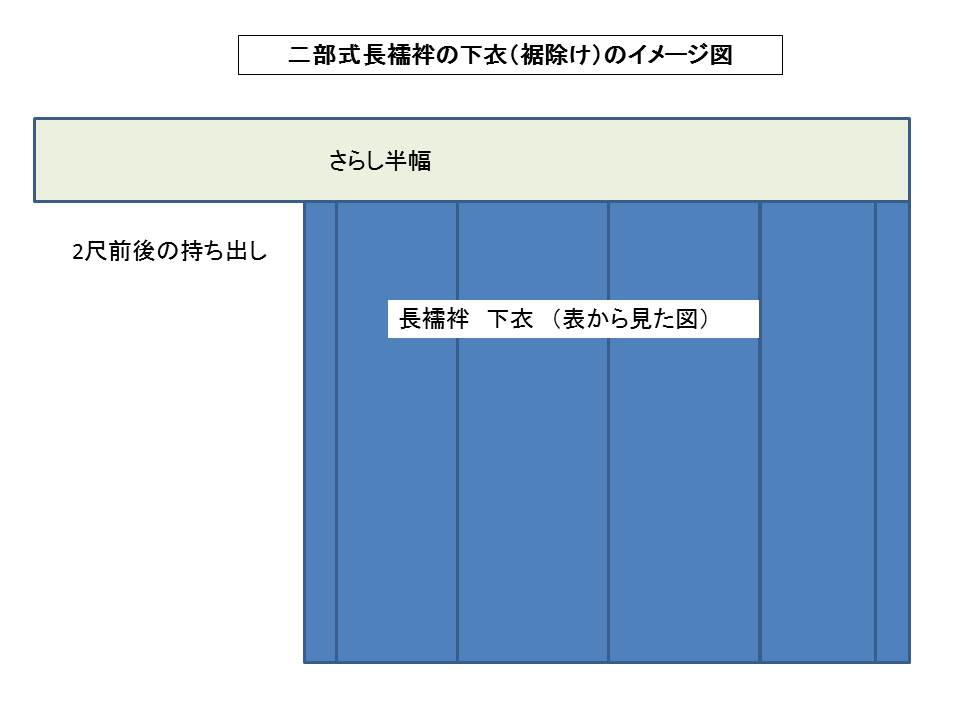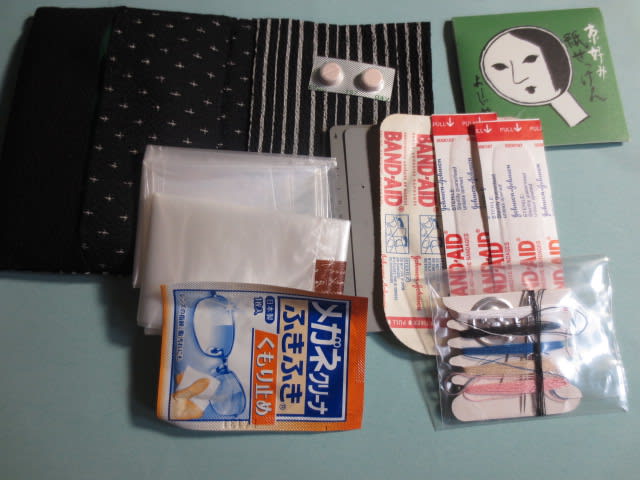前回の洒落袋帯の直しに続いて もう一本 帯の芯を入れて仕立て上げました
こちらは芯は入れなくても大丈夫かもと言われたのですが、入れてみることにしました
そして今回も 垂れ先に無地場を使うことに
芯を入れなくてもいい帯ということで、2枚が縫い合わさっているものの、縫い代はぎつぎつ
狭いところでは 5ミリもありませんでした
前回と同じように 50センチに3ミリほどの芯にゆとりを入れての 芯張り
3寸おきに小針に返して 狭い縫い代に留めた芯が なにかの拍子外れたりしても 返し針でダメージを最小限になるように
芯を閉じ付けて 表に返してみると、なんと2か所 閉じ付けた糸が表まで出ているのです
でもやり直す気力はなく、糸を切って帯の中に消えさせるという横着を
でも 小針に返し針をしてほつれ止めになっているので、1~2か所糸切れ起こしても大丈夫だろうと思っています
前回の帯に使っていた芯を再利用したのですが、まったく重さを感じません
帯の種類によって 重さも変わってくるのですねぇ
この帯は 締めてみて芯が邪魔なようでしたら 芯抜きのつもりです
こちらは芯は入れなくても大丈夫かもと言われたのですが、入れてみることにしました
そして今回も 垂れ先に無地場を使うことに
芯を入れなくてもいい帯ということで、2枚が縫い合わさっているものの、縫い代はぎつぎつ
狭いところでは 5ミリもありませんでした
前回と同じように 50センチに3ミリほどの芯にゆとりを入れての 芯張り
3寸おきに小針に返して 狭い縫い代に留めた芯が なにかの拍子外れたりしても 返し針でダメージを最小限になるように
芯を閉じ付けて 表に返してみると、なんと2か所 閉じ付けた糸が表まで出ているのです
でもやり直す気力はなく、糸を切って帯の中に消えさせるという横着を
でも 小針に返し針をしてほつれ止めになっているので、1~2か所糸切れ起こしても大丈夫だろうと思っています
前回の帯に使っていた芯を再利用したのですが、まったく重さを感じません
帯の種類によって 重さも変わってくるのですねぇ
この帯は 締めてみて芯が邪魔なようでしたら 芯抜きのつもりです





















![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/154cb54c.863a3b67.154cb54d.d15a236c/?me_id=1234932&item_id=10000862&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuichikimono%2Fcabinet%2Fkomono1-main%2F80048429.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuichikimono%2Fcabinet%2Fkomono1-main%2F80048429.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)