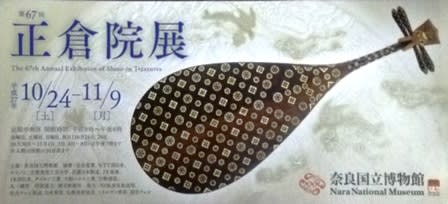二か月ほど前のこと。
眠れぬままに いろいろと考え事をしていたら、急に木工がしたくなりました
そこで、『 はやりあれが欲しい! 』 と つぶやいたら
珍しくトトさんが反応して 何が欲しいのかしきりに聞くのです
言っても 一笑に付されるだろうと 最初は濁していたのですが、しつこく聞くので
『 テーブルのついた電動丸鋸が欲しい。 あれがあれば、私でも木工が出来そうだから 』 と 言ってみました
すると、実はトトさんも欲しかったのだという
一般的には おとこのすなる木工なのだから、さっさと買って 上手にいろいろと細工をしてくれれば 嬉しいのに どうやら 背中を押してもらいたかった?
翌朝 早くからネットで検索して 私にいろいろと説明しだしました
あまりにも安いい商品だと おもちゃの域を出ないような気がして そこそこの商品を検討
そして読者のレビューを参考にして 一つのテーブルソーを選びました
やっと届いて 梱包を開けて 組み立てに要したこと 半日 ‥‥ トトさんの仕事
傍らで私は 『 一歩間違えば 凶器にもなりかねない道具だから 慌てずに慎重に! ボルトはしっかりと締めて!』
組み立て終わって 試しに板をカットしてみると なんと簡単に綺麗に切れることか ‥‥ 私も簡単に使えそう
カットされた断面もすべすべに近い状態で やすりの必要もなさそうです
私は まずは 味噌麹の発酵器が作ってみたい
棚板も増やしたい
庭用の作業テーブルも作ってみたい
楽しそうなことが次々に浮かびます
で、欲しいと言っていたトトさん 何に使うのか 一言も聞いてないなぁ
ソーイングマシン(ミシン)に 比べてはるかに安い買い物でした
トップの画像は アマゾンさんからお借りしました
眠れぬままに いろいろと考え事をしていたら、急に木工がしたくなりました
そこで、『 はやりあれが欲しい! 』 と つぶやいたら
珍しくトトさんが反応して 何が欲しいのかしきりに聞くのです
言っても 一笑に付されるだろうと 最初は濁していたのですが、しつこく聞くので
『 テーブルのついた電動丸鋸が欲しい。 あれがあれば、私でも木工が出来そうだから 』 と 言ってみました
すると、実はトトさんも欲しかったのだという
一般的には おとこのすなる木工なのだから、さっさと買って 上手にいろいろと細工をしてくれれば 嬉しいのに どうやら 背中を押してもらいたかった?
翌朝 早くからネットで検索して 私にいろいろと説明しだしました
あまりにも安いい商品だと おもちゃの域を出ないような気がして そこそこの商品を検討
そして読者のレビューを参考にして 一つのテーブルソーを選びました
やっと届いて 梱包を開けて 組み立てに要したこと 半日 ‥‥ トトさんの仕事
傍らで私は 『 一歩間違えば 凶器にもなりかねない道具だから 慌てずに慎重に! ボルトはしっかりと締めて!』
組み立て終わって 試しに板をカットしてみると なんと簡単に綺麗に切れることか ‥‥ 私も簡単に使えそう
カットされた断面もすべすべに近い状態で やすりの必要もなさそうです
私は まずは 味噌麹の発酵器が作ってみたい
棚板も増やしたい
庭用の作業テーブルも作ってみたい
楽しそうなことが次々に浮かびます
で、欲しいと言っていたトトさん 何に使うのか 一言も聞いてないなぁ
ソーイングマシン(ミシン)に 比べてはるかに安い買い物でした

 | E-Value 木工用テーブルソー 255mm ETS-10KN |
| クリエーター情報なし | |
| イーバリュー(E-Value) |
トップの画像は アマゾンさんからお借りしました







































 ( 数回経験済みです )
( 数回経験済みです )