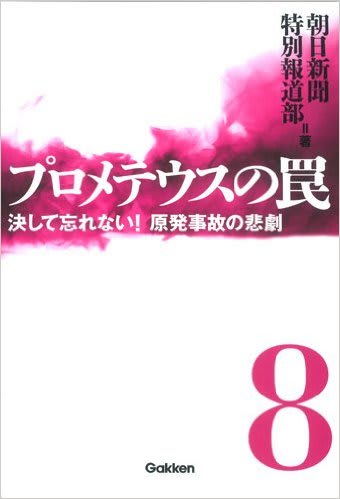
朝日新聞特別報道部
『プロメテウスの罠8
決して忘れない!原発事故の悲劇』★★★★
装丁の色が目を惹く。
中身も濃く今回はちょっとテイストがちがうように感じた。
何も知らない頃に比べて意識が変わったせい?
だからと言って何かを出来ているわけではないのだけれど。。
知らないことが多すぎる。
声を大にして言いたい。言いたくなる。
どうしてもっと発信されないのだろうと。
2014年8月6日 連載は1千回の節目を迎えた。
福島が、忘れられはいまいか。
心に刻む4年目である。
---
結局はおカネでしょ
「最終処分場の話は、最後は結局おカネでしょ?」
「受け入れてくれないとなったら、お宅にはその2倍払いましょう。それでも手を挙げてくれないんだったら5倍払いましょう。10倍払いましょう。どっかで国民が納得する答えが出てきますよ」
核燃サイクル路線をとって再処理工場を40年間動かすと19兆円のコストがかかる。工場建設費が予定の3倍に膨らんだことを考えると、核燃サイクルは総額で50兆円を超えるコストになるかもしれない――。
日本はすでに44トンのプルトニウムを国内外に持ち、それは長崎型原爆の5千発分以上に相当する。
すでに「アリ地獄」
「原発を動かすと、10万年ものあいだ放射線を出し続ける核のごみが出てくる・・・・・・だからこそ、(それを再処理して燃料に使う)『もんじゅ』は動かさなくてはならない。原子力ムラの飯の種を維持するため、『もんじゅ』が動くといい続けないと、原子力の神話が崩壊する」
核燃サイクルの柱である「もんじゅ」は、すでに霞ヶ関で「アリ地獄」といわれている。
「何の研究もせずに単に維持するだけで、毎年200億円が必要とされています。昭和55年以降、1兆円以上を投入しておきながら、何の成果もない。この費用対効果を国民に説明できるのでしょうか」
早期の帰還が難しい大熊、双葉、浪江、富岡の4町と、住民が戻り始めている広野町と川内村、帰還時期の検討をしている楢葉町では、復興のイメージがまちまちだ。同じ被災地でも事情が違いすぎた。
「わたしたちは原発の安全神話にどっぷりつかっていたために大変な目にあった。子どもたちには、自分の足で立ち、自分の頭で考える人間になってほしいのです」
宮内庁で両陛下の意向を直接聞く立場にいるのは二人だけだ。
一人は宮内庁長官。「オモテ」と呼ばれる事務方のトップだ。
もう一人は侍従長。「オク」と呼ばれる、両陛下の身の回りの世話する侍従長のトップである。
双葉町民が移ってきたばかりの校舎内をくまなく下見した。それをもとに天皇と皇后が歩く動線の案を決める。県内の立ち寄り場所や、到着・出発時刻の見通しなどをA4判1枚の図にまとめた。目的地の間を線で結んで予定時刻が書き込まれ、全体を横長の箱型の表に入るようにつくられた日程表は「ハコ日程」と呼ばれるものだ。
津波の避難誘導や堤防見回りをした消防団員ら二百数十人が亡くなったと話した。
両陛下は絶句して、目をうるませたようだった。
両陛下の地方訪問は、ものによっては1年以上前から日程が決まっている。宮内庁と警察、自治体や交通機関が打ち合わせ、分刻みで日程を決める。警察は他の車を排除し、信号を全部青にするのが通常だ。しかし東北3県は、沿岸警備に多数の警察官をさける状況ではない。
そこに宮内庁から「被災地に負担をかけないように」との両陛下の意向も伝わった。そこで、車で移動する距離をできるだけ短くし、沿岸警備の人手が少なくすむように、ヘリが着陸するグラウンドに隣接した避難所を訪問先とすることにした。
「陛下、日本人って捨てたものじゃないですね」
「両陛下は、放射線についてはとくに子どもたちへの影響を深く気にかけておられました」
「自分が行きたい場所よりも、相手が『ここへ来てほしい』と用意した場所へ行く。それが訪問先に対する誠意だ――というのが、これまでの陛下の基本姿勢でした」
しかし今度の大震災では、天皇側からの強い意向が働いた。被災地の訪問は、いずれも宮内庁側から打診して実現している。
地震や津波、原発や放射能の専門家や行政機関の長ら二十数人を次々と御所に呼んで説明を受け、予定時間を超えても質問を続けた。避難所で被災者に寄り添う姿は、事前の膨大な準備と努力に裏打ちされていたのだった。
「天皇は、災害もまた自分の責任と考えているのかもしれない。宮中祭祀で国民の平安を神に祈る熱心な姿と、災害地を訪れて被災者を直接に慰める姿は、表裏一体といえるのではないかと思います」
被災地で救援活動に携わった自衛隊員や警察、消防、自治体職員の多くが、両陛下から「ありがとう」と声をかけられている。
「被災した人々や全国民に代わって『ありがとう』とおっしゃったともいえる。いろいろなお気持ちが全体からにじみ出るようなものではないでしょうか」
「いわきは安全。気をしっかり持って生活してほしい」
「怖がることはない。これを伝えるために私たちがいわきを訪れた」
「いわき市民が踏みとどまることが、日本の安全安心につながる」
「飯館村は避難が必要な汚染レベル。福島第一原発では放射能が出続けており、汚染度の高い地域はチェルノブイリ級といっていいだろう」
「いくらもがいても、泣いても、原発から出てしまった放射能には勝てません。悔しさで胸が裂けそうな毎日を送っております」
「原発作業員でもない一般の住民が、線量計をぶら下げながら生活するなんて・・・・・・」
結局、カネを積んで住民を早く帰還させ、かたちばかりの復興を急ごうということじゃないのか――。
東京電力は「仕事をくれるお得意さん」だった。しかし今となっては、暮らしを奪った加害者でしかない。
「カネの問題じゃない。いのちの問題なんだ」
「阿武隈山系の地下水は軟水でおいしいんだ」
井戸は深さ10メートルほどもある。しかし時間がたつにつれ、山中の地表に沈着した放射性物質が地中深く染み込み、水が汚染されやしないか――。そんな不安をぬぐえない。
地域では「まるで人体実験」と計測を拒む住人も少なくない。
被爆線量は、個人線量計のほうが従来の空間線量による推計値より低く出る傾向にある。
政府は「復興加速化」というが、加速するのは過疎化じゃないか。
2014年3月18日(火)
福島県議会の平出孝朗議員が、原発立地・立地予定の14道県の道県議会議長でつくる
「原子力発電関係道県議会議長協議会」から脱退すると表明。
「他県の議長らは原発再稼動を前提にしている。同じ会に入っていることに違和感がある」と
---
昨日歩いていてふと弟のことについて一つの結論が出た。
ざわめきはなくこころは静かだった。























