
(父に似たのは一目瞭然・・
昭和でも平成でも令和でもない。
あとみかんも・・

秀峰富士
お金さえあれば誰でも登れる!?
https://www.evernew.co.jp/outdoor/yamanoi/





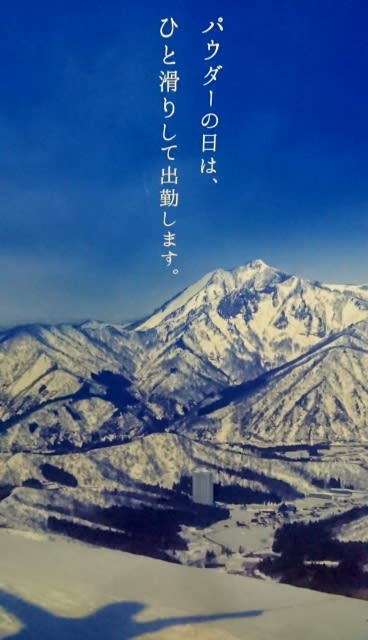









あまり知られていない私の仕事、富士山の強力の話 | 山野井通信 | EVERNEW
今回は、あまり知られていない私の仕事、富士山の強力の話を書きます。富士山頂の気象庁の観測所への荷上げを始めて10年以上になります。
山野井通信 | EVERNEW
http://www.evernew.co.jp/outdoor/yamanoi/2002/20020131.html




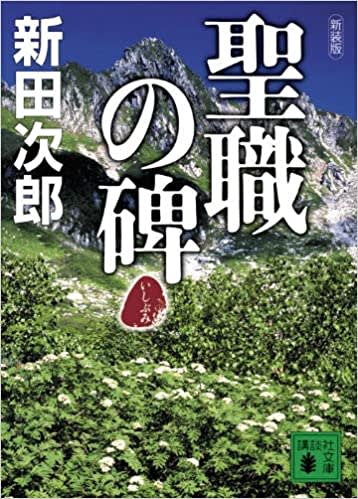

新田次郎
『冬山の掟』★★
初出は昭和53年7月
文庫としての新装版
山岳短編集
昭和感漂う一作もあるけど、山に関しては40年経過した今読んでも変わらない。
自然に対してハイテク機器は通用しない。
GPSは便利な機能だとは思うけど。
しかし・・救いようのないのが冬山
注意喚起小説でしょうか。
助かってほしい!そんな思いも空しく視界がきかない。
身体の感覚が失われてゆく。そして急激に訪れる睡魔・・
今週末はボードだけど、改めて吹雪の怖さを再確認(先日かぐらで死亡事故があったばかり)



先日の棒ノ嶺でも記載したけど登山での道迷い。
道が狭くなり、気づいたら踏み跡が消えている。
どう考えても違う道と気づく。
その時点での判断が重要とされている。
素直におかしいなと思ったら戻る(これ基本)
何となくだけど、男子はそのまま突き進む人が多い気がする。
(男尊女卑は問わない)
自信?プライド?下手な経験?
その時点でわたしは目印を決めておき、突き進むに付き合うけど、結局はその目印まで戻ることが多い。
ほーら言ったじゃん!
登山歴や経験以上に人柄が出る。ゴルフみたい。
行き当たりばったりだけど怖い目に合ったことがない。
勘というか何なのか。
人間の五感が研ぎ澄まされるのが山
山をなめるなって?
低山専門なのはそのせいかもしれない。
なので登り納めがない(笑)

続けて読んだのが『聖職の礎』史実に基づいた小説。
ドキュメンタリー山小説よき!
