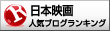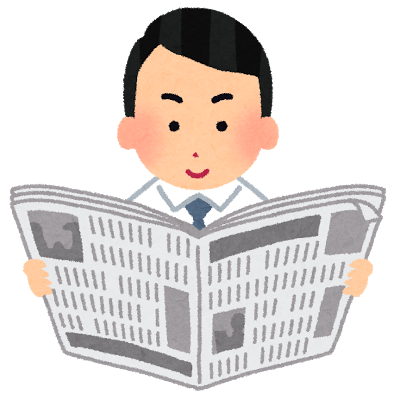「行動経済学の処方箋」
大竹文雄著、中公新書、2022年11月
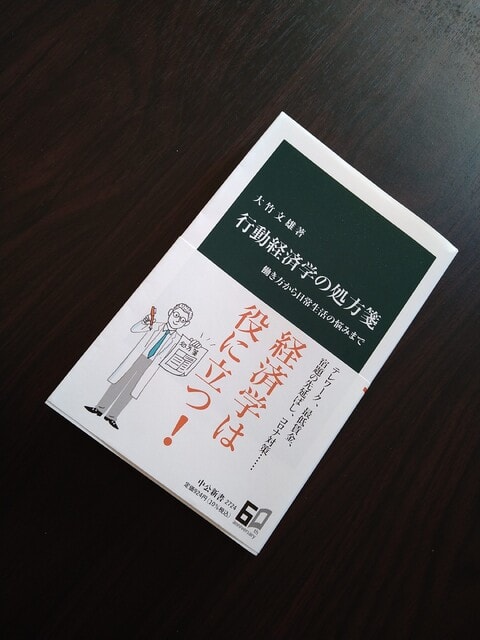
働き方から日常生活の悩みまで、
最新の経済理論を駆使して処方箋を示した本。
タイトルに「行動経済学」とありますが、本書も含め、「行動経済学」が指す分野が広がってきたよう思います。
伝統的な経済学の理論を、実験を通して立証・反証することも行動経済学に含まれる印象です。
著者の大竹文雄氏は主に関西方面で活躍されている経済学者で、著書も多数あり、自分も新書のみ何冊か読んでいます。
コロナ対策専門家会議のメンバーでもあるそうです。
本書の半分くらいは海外の行動経済学者が執筆した書籍と同じような話。
半分はコロナ対策やテレワークなどを経済学の視点から解説しています。
日本の文化・習慣や日本人の習性も踏まえている点も海外の学者の書籍とは違います。
コロナ禍において国が発出してきた外出自粛、飲食店休業、ワクチン接種等のメッセージは行動経済学的知見に基づいて作られたそうです。
ただ対策自体は大竹氏の意向が常に反映されていた訳ではなかったようで、
コロナウイルスの変化、治療法・ワクチンの進化に応じて対策を見直すべきではなかったか、という趣旨のことを述べています。
「(感染症対策も重要だが、)他の重要なものを失ってしまっているというリスクに気づかなかったり、過小評価したりしているのではないだろうか」(P.96)
自分もそう思います。
テレワークのメリット・デメリットについても共感できる部分が多いです。
同僚と一緒に仕事をすることで、お互いに監視されている感覚があって手を抜けなかったり、同僚が頑張っている姿を見て自分も頑張ろうと思えたり、同僚の立ち振る舞いを見て自分の行動の参考にしたりして、生産性が上がるということはあると思います。
もちろんメリットもあり、自分も週何日かはテレワークを続けたいです。
目次:
プロローグ 経済学の常識、世間の常識
第一章 日常生活に効く行動経済学
第二章 行動経済学で考える感染対策
第三章 感染対策と経済活動の両立
第四章 テレワークと生産性
第五章 市場原理とミスマッチ
第六章 人文・社会科学の意味
エピローグ 経済学は役に立つ

関連エントリ:
競争と公平感
大竹文雄著、中公新書、2022年11月
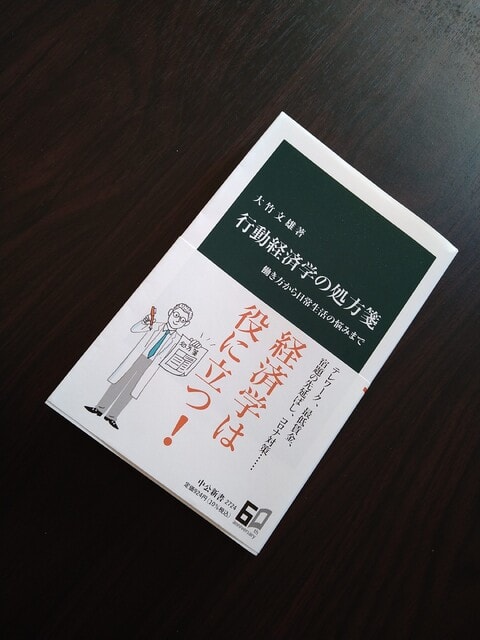
働き方から日常生活の悩みまで、
最新の経済理論を駆使して処方箋を示した本。
タイトルに「行動経済学」とありますが、本書も含め、「行動経済学」が指す分野が広がってきたよう思います。
伝統的な経済学の理論を、実験を通して立証・反証することも行動経済学に含まれる印象です。
著者の大竹文雄氏は主に関西方面で活躍されている経済学者で、著書も多数あり、自分も新書のみ何冊か読んでいます。
コロナ対策専門家会議のメンバーでもあるそうです。
本書の半分くらいは海外の行動経済学者が執筆した書籍と同じような話。
半分はコロナ対策やテレワークなどを経済学の視点から解説しています。
日本の文化・習慣や日本人の習性も踏まえている点も海外の学者の書籍とは違います。
コロナ禍において国が発出してきた外出自粛、飲食店休業、ワクチン接種等のメッセージは行動経済学的知見に基づいて作られたそうです。
ただ対策自体は大竹氏の意向が常に反映されていた訳ではなかったようで、
コロナウイルスの変化、治療法・ワクチンの進化に応じて対策を見直すべきではなかったか、という趣旨のことを述べています。
「(感染症対策も重要だが、)他の重要なものを失ってしまっているというリスクに気づかなかったり、過小評価したりしているのではないだろうか」(P.96)
自分もそう思います。
テレワークのメリット・デメリットについても共感できる部分が多いです。
同僚と一緒に仕事をすることで、お互いに監視されている感覚があって手を抜けなかったり、同僚が頑張っている姿を見て自分も頑張ろうと思えたり、同僚の立ち振る舞いを見て自分の行動の参考にしたりして、生産性が上がるということはあると思います。
もちろんメリットもあり、自分も週何日かはテレワークを続けたいです。
目次:
プロローグ 経済学の常識、世間の常識
第一章 日常生活に効く行動経済学
第二章 行動経済学で考える感染対策
第三章 感染対策と経済活動の両立
第四章 テレワークと生産性
第五章 市場原理とミスマッチ
第六章 人文・社会科学の意味
エピローグ 経済学は役に立つ

関連エントリ:
競争と公平感