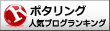2023/6/12(月) 晴/曇
今日は最高気温31°の真夏日の蒸し暑い日だが、明日も雨模様の天気予報に午後14時半からポタリングに出る。目的地を山鹿市の聖母八幡宮とする。
久野湧水群を後にして、北方向に進むと、千田聖母八幡宮(写真8参照)が鎮座する。

立派な楼門(写真9参照)がある。楼門には「霊廟」の扁額が掲げてある。

境内拝殿右側に由緒等を書いた説明板(写真10参照)が掲示してある。
その由緒沿革には、「反正天皇三年(408)信託により聖母大神宮として勧請し、神功皇后を祭祀す。後世宇佐八幡宮(應神天皇、仲哀天皇)を合祀、千田聖母八幡宮と称す。其の後朝庭の崇敬厚く五十代桓武天皇御宇延暦八年(789)神殿、拝殿、楼門、連歌堂、御祈祷所、廻楼、仁王門、末社・一・二・三鳥居勅命にて造営あり。建久二年(1191)源頼朝公各殿宇を改築せられ益々御神威盛なり。当後深草院御宇、北条時頼公社殿堂を修復せられしが天正三年(1582)薩州之守嶋津(修理太夫)義久公桜田参河守を建築奉行として再建す。又菊池家及び細川家の崇敬厚かりき。」とある。
408年とは古墳時代だが記録があったのか、それとも反正天皇三年の西暦変換が違っているのか疑問が残る。ここを折り返し点として帰途に就く。

19時に帰宅する。今日も無事だったことを天に感謝する。
熊本(自宅)26km→聖母八幡宮25km→熊本(自宅)
総所要時間4.5時間(実4時間) 総計51km 走行累計54,249km
千田聖母八幡宮
2016/9/5(月) 晴
今日の台風は天草西海上を北上し、昼から熊本の天候は上がったので15時半から短距離ポタリングに出る。気象庁観測値の気温は16時32度。例により熊鹿ロードを北進する。
今日の目的地は、山鹿市千田聖母八幡宮。
聖母八幡宮の由緒書には、沢山の神様の名前が列挙されている。その神様の名前を再確認したいと思う。
三の鳥居の横に境内見取り図が掲示してある(写真1参照)
境内摂社の謂れも知りたいと思う。

立派な楼門がある。拝殿横に由緒書がある。
境内摂社の神々は、神功皇后熊襲征討軍の神々とは限らないようである(写真3参照)。

聖母八幡宮の創建は西暦 408年と言う(写真4・5参照)
反正天皇は神功皇后のひ孫にあたる。神功皇后は四代溯るので3世紀末か4世紀初の神か?「神功皇后=卑弥呼」説もあるが、年代が合わない。
飛地境内の八嶋八柱の神々は、この国を造った景行天皇以前の神々のこと理解した。
八つの光と頭八つの亀とは沢山の先住部族で、征討された側で間違いなかろうと思う。


熊本市北区植木町清水菅原神社に「神功皇后の放った弓矢が刺さり云々」と言う伝承がある(2016/6/17の記事参照)。
この地で在地の神々と北から来た新興の神々の死闘があった、そんな記憶から消し去ることの出来ない歴史遺産であろうと思う。
夕方のことであり、写真を撮ると早々に帰途に就く。
今日も無事だったことを天に感謝する。
熊本(自宅22km→千田聖母八幡宮22km→熊本(自宅)
所要時間3.5時間(実3時間) 総計44km 走行累計18,036km
追記2017.7.8
徐福=ユダヤ人説の本を読んで疑問に思ったことをWeb検索していたところ、このページの拙文をご評論いただいている「ひぼろぎ逍遥 古川 清久氏」のブログ(http://hiborogi.sblo.jp/article/175719284.html)に辿り着いた。
さて、そのブログによれば「八嶋八神」は、九州王朝を支えた神々で、蹴破りで茂賀浦湖が失われたとき滅んだ海神族の痕跡ではないとのことである。
「八嶋八神」を祀ったのは、神社由緒書では景行天皇、熊本県神社誌では神功皇后となっている。
仮に神功皇后だとして、「八神を祀り戦勝を祈願せられた」のが何故山鹿市千田だったか?
単に戦勝祈願であれば、「香椎の宮」でも出来たと考える。
熊本には神功皇后の征討伝説があり、祀ったのは「八神」の名において半島遠征のため兵員・戦費調達の征討行軍を行ったのではないかと推察した。
神像に剣唐花紋があるとのこと。その意味するところは?
千田聖母八幡宮
2015/11/1(日) 曇
天候は曇。今日のポタリングは、山鹿市鹿央町
熊鹿ロードを北へ走り、道の駅「夢大地館」へ。
まずは昼食を取り、聖母八幡宮(写真1参照)へ参拝。

改めて由緒書(写真2参照)を読む。
「反正天皇3年(西暦408年、第18代)神託により・・・」とあるので、その通りであれば古墳時代前期には建立されたことになる。
景行天皇(第12代)、神功皇后、仲哀天皇(第14代)、応神天皇(第15代)と天皇名があるが、この辺りは景行天皇の頃は茂賀の浦と言う湖であり、神功皇后の頃干拓されたことになるようだ。この功績を称え祭神としたと考えられる。
この神社と同じ等高線上の植木町加村地区に阿蘇一宮が有り、阿蘇健磐龍命の蹴破り伝説も根拠のない話ではないようだが、歴的事実かどうかは不明。
聖母八幡宮の場所:(マップファン地図)
千田聖母(しょうも)八幡宮
2015/1/24(土) 晴
今日のポタリングの目的地は、「千田聖母(しょうも)八幡宮」。午後1時半出発。
古墳を後にして千田方向へ走る。途中、道の両側に塚状の豊前街道五里木跡という標識がある。
その先の「千田浦大間古墳跡」の標識を見て右折する。
千田川の谷筋に下る手前にそれはある。
古墳跡の所を右折し、坂を下れば千田地区。
以前から「千田」の地名が気になっていたが「大国主命=大巳貴(おほなむち)=海と大地の主神」の「チ=神」のことのようで「千田=神の田」で納得する。
肥後には、国道266で緑川を渡った所に「千町」と言う地名がある。
藤井耕一郎氏の著書「武内宿祢の正体」に、ウチとは「海(ウ)の霊(チ・海の勢い)」とあった。(2010.10.20追記)
八嶋公園の先の鳥居を潜り千田川を渡れば、「千田聖母八幡宮」の参道の石段に続く。石段を登り山門を潜る。(全体イメージ写真がなくてすみません)
山門の額が「霊廟」(写真3参照)となっている。

早速参拝し由緒書(写真4参照)を読む。408年創建とあるが古墳時代のこと、年代は大きくは違わないと思うが検証はされていない時代のことである。

八頭の亀退治の話は、八嶋八柱として祀ってあるところを見れば、先住部族と争った結果としてその霊を恐れて祀ったとも想像できる。
八嶋八柱は、高皇産霊日神(たかみむすびのかみ)、神皇産霊日神(かみむすびのかみ)は天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)=皇産霊日神(たまつめむすびのかみと同神という説もある)天地開闢のときの造化三神として最初に高天原に現れた神様、延喜式神名帳にある八座の神々という。(この段参照、HP玄松子の記憶・生産霊神より)
徐福伝説とも関りのある神様で、徐福は3000人の技術者集団とともに日本にやってきたという。
断片的に思い付きを記せば、八代妙見宮のシンボルが亀。
八嶋神社地の標高が海抜30m、内田川沿いの上梶屋、下梶屋地区が海抜30mで茂賀の浦湖岸?に位置する。
「八つの光が昼夜わかたず見えしに」とは製鉄所か?そこに八龍神社が鎮座する等、疑問が膨らむ。
帰路は、道の駅「夢大地館」に立ち寄りエネルギーを補給する。
今日も無事だったことを天に感謝する。
熊本(自宅)23km→「千田聖母八幡宮」23km→熊本(自宅)
所要時間4時間(実3.5時間) 総計46km 走行累計9,623km
千田聖母八幡宮・八島伝説
2015/1/12(月) 晴
台地に上がる前に、千田川河畔にある八つ頭の大亀を祭ったという伝説(写真1参照)がある八島公園に立ち寄る。

千田川を挟んで対峙するように408年?神功皇后を祭神として勧請したという「千田聖母八幡宮」がある。
古代湖「茂賀の浦」の水が退いたのが1700年前。綿津見系 の神様と八幡系の神様が争ったのか?
山鹿、植木地方には海神系と八幡系の神社が対峙する様に存在する地域が多くあるという。(この段参考HP:古代湖「茂賀の浦」から狗奴国へ)
千田は千枚の田か?ここから1.5km程の所の宮原には鉄分が濃い赤茶色の温泉がある。この地にも温泉が湧いていてその色からの連想の地名か?
植木町菱形の八幡宮が日本最古とすれば、その年代が気になるところである。