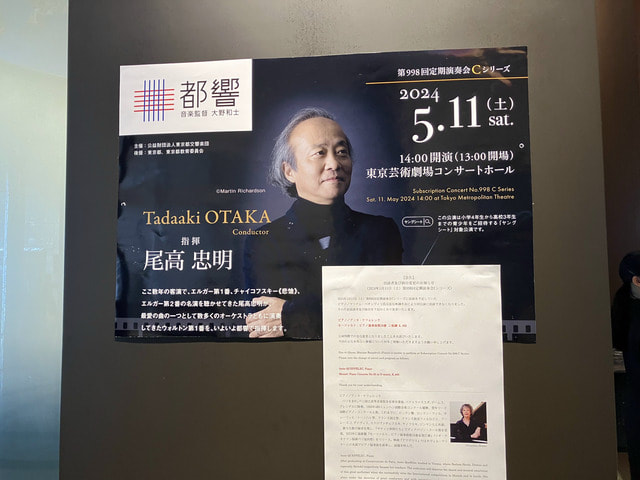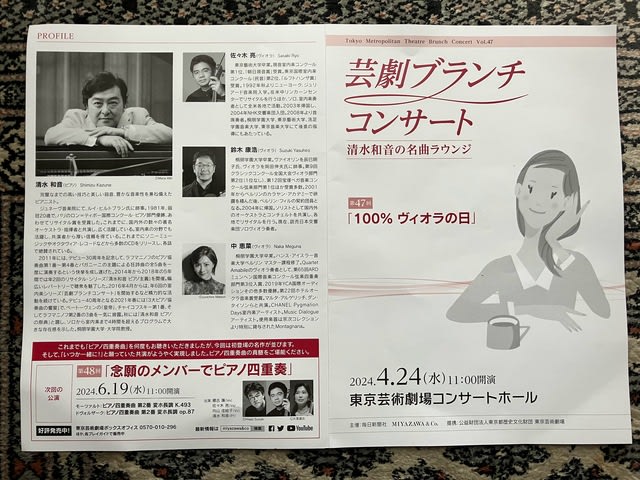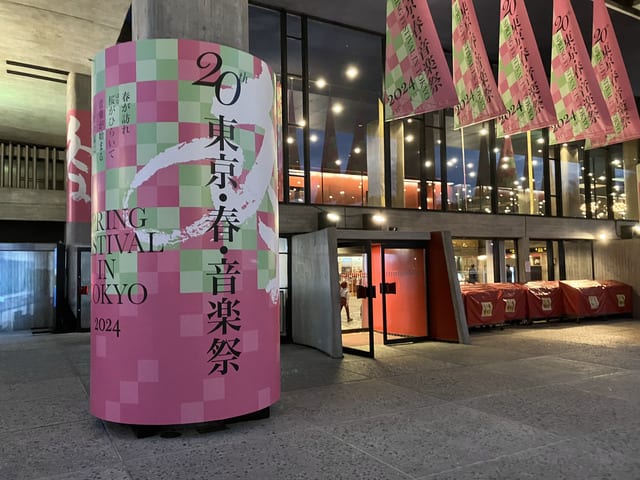NHKプレミアムシアターで放送していた「マケラ指揮コンセルトヘボウ管2023&ドキュメンタリー」を観た
クラウス・マケラ指揮、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団演奏会2023、ソプラノ:ヘン・ライス(2023/12/25、コンセルトヘボウ)
- 序曲「フィンガルの洞窟」(メンデルスゾーン)
- 「ヘーローとレアンドロス」(ファニー・メンデルスゾーン)
- 「夏の夜の夢」からスケルツォ(メンデルスゾーン)
- 演奏会用アリア「不幸な女よ」(メンデルスゾーン)
- 「交響曲第3番」(ベートーベン)

今回の演目ではベートーベンの3番に注目した、彼の経歴からシベリウスやフランス音楽が好きなのではないか、と勝手にイメージしていたので、ドイツ物の中でも最大の作曲家のベートーベンの3番をどう指揮するか注目していた。ただ、あとに述べる彼のインタビューでは、最初に好きになったのはモーツアルトと言っているので、ドイツ物は好きなのかなと思い直した。
今回の3番は、全体的には満足する演奏だったが、第4楽章のスピードが早すぎると感じた、もっと重厚感のある、また、切れ味鋭い演奏が好きだ。演奏スピードが速すぎるとそれが出せない、逆に軽い感じの演奏になってしまうと思っている。





ドキュメンタリー、クラウス・マケラ、ほとばしる情熱
クラウス・マケラ(1996、フィンランド)は28歳の若さ、チェロ奏者であり、指揮者である。指揮者としては既に2020年にオスロフィルの首席指揮者、2021年にパリ管弦楽団の音楽監督になどに就任し、2027年からロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者に、さらに2027年9月から5年間、シカゴ交響楽団音楽監督に就任することが発表されている

このドキュメンタリーはマケラの来し方や指揮に関する考え方などをインタビューを中心にして描き出すものである。彼がどんな風に音楽に親しみ、職業とし、成長してきたのかを描いている非常に興味深い内容だ。
このドキュメンタリーを観て、マケラが若いのにしっかりとした考えを持つ人間であり、オーケストラメンバーなどチームワークを立派にこなせる人間だということがわかる。





このドキュメンタリーの中でマケラが述べていることで、なるほどと思わせることや参考になったことを少し書いてみよう
- 指揮というのは不思議な仕事で、演奏におけるその役割も簡単には説明できない、大切なのは信念であり、自らの知識と情熱をいかに演奏に反映するかだ
- 演奏者が望むものは良い演奏をさせてくれる指揮者だ、それさえできれば脚を使おうが目で合図をしようが構わない
- 最初に好きになった音楽はモーツアルト、今も心の支えだ、自分が育った環境は穏やかで、音楽にあふれていた、両親も親類も音楽家ばかり、でも強制されなかったのは幸いだった、
- 自分は神童ではなかったが、父が持ってきたチェロを始めて音楽が一層好きになり、楽譜を見たり曲を聴いたりしていた、本気になったきっかけはオペラだ、指揮者はチェロ奏者と違い、オペラのすべてを演奏できるからだ、それで指揮者になりたいと思った
- シベリウスアカデミーの指揮のジュニアコース試験会場に行ったとき、ヨナス・パルマがいた、だれもが知る巨匠で名教師、彼に認められて指揮者になる指導を受けた、パルマは指揮者の指示は最小限でいい、講釈は必要ない、少ない動きで技術的な信条を伝えることを学んだ
- 楽団のメンバーとは仲がいいから演奏もよくなる
- 指揮者も演奏家だと思っている、指揮者がオーケストラの楽器を何一つ演奏できなかったら高い技術を持つ演奏家たちに指示など出せない
- 指揮者は何か言うのに3回は我慢する、オケの演奏をいちいち止めて細かい指摘をするのは時間の無駄だ、でも室内楽は意見の交換が重要だ

テレビでは触れられていなかったが、なぜ彼がこんなにも若く頭角を現せたのか。それはおそらく、音楽一家に生まれて家族から英才教育を受けたことや、音楽一家に生まれたメリットを最大限活用できたこと、強力な支援者がいたこと、ヨーロッパ社会が実力ある若手を育てていく素地があることなどかもしれないが、それは想像でしかない
本当の成功要因というものを知りたいし研究する必要があるのではないか、なぜならマケラのようなことは日本では考えられないからだ。マケラは指揮者コンクールなどで優勝したわけでもない、そんな若手を優秀だからと言って抜擢するだろうか、オケのメンバーたちは快く受け入れるであろうか、そこが日本にはない欧州の強さかもしれない